-
平日9:00-18:00
- mail お問い合わせ
マニュアルアカデミー
- ホーム
- マニュアルアカデミー
- 業務標準化とは?得られる効果や成功させるためのポイント
業務標準化とは?得られる効果や成功させるためのポイント
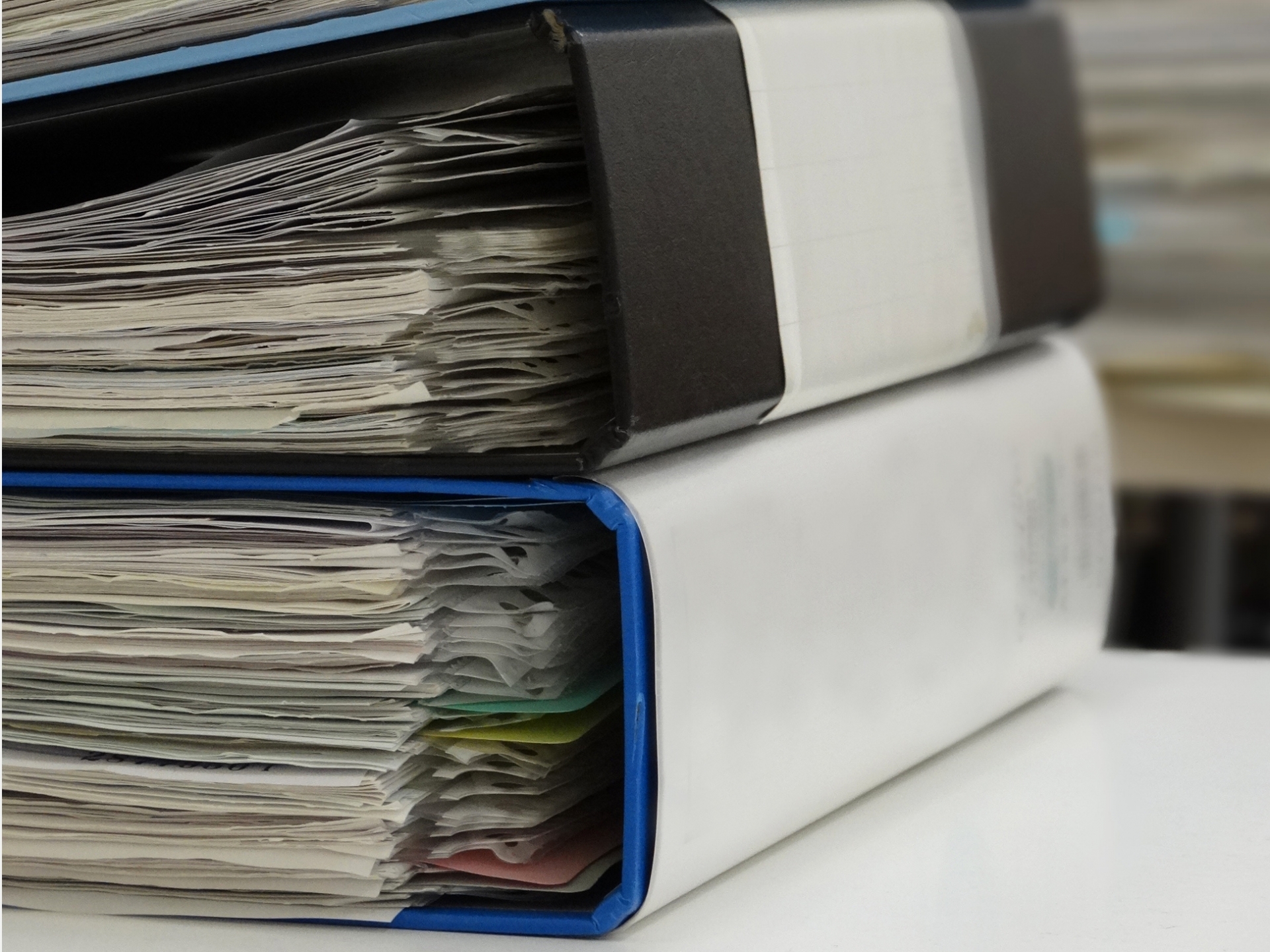
特定の従業員に負担が集中したり、作業品質に偏りが生じたりする場合は、業務標準化に取り組むことが有効です。
ただ「そもそも業務標準化とは何かよくわからない」という方もいるのではないでしょうか。
そこで、本記事では業務標準化とは何か、実施することでどういった効果が得られるのかなどについて解説します。進めていくための流れやポイントも詳しく紹介するので、ぜひ参考にしてください。
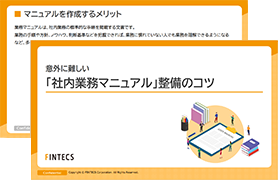
プロが解説!マニュアル作成のコツ
500社以上のマニュアルを支援してきたマニュアル作成のプロが業務マニュアルの作り方を解説しています。
業務標準化とは
業務標準化とは、組織内の業務や作業手順に基準やルールを作り、組織全体で同様の形になるように取り組んでいくことをいいます。
これにより、誰が行っても品質や成果が同じになり、個人の能力による違いや品質差が生まれにくくなります。
たとえば、同じ経理内でも人によって費用の勘定科目が違うケースがありますが、こういったものもルールを決めて統一することでどの勘定科目を使うべきかわかりやすくなります。
現在は属人化している作業に関してもマニュアルや業務フローを参考に進められるように整備すれば、属人化の解消が期待できるでしょう。
関連記事
「業務効率化の方法とは?実施するメリットと具体的な手順を確認」
業務平準化との違い
業務標準化と似たような言葉として「業務平準化」があります。
業務標準化は、業務手順やルールを統一し、誰が作業をしても同じやり方・成果物になるように整えるためのものです。
大きな目的は属人化の解消にあると言えるでしょう。
一方で、業務平準化とは、日々の業務における負荷や作業量といったものを分散させることで一部の従業員や特定の時期のみに業務が偏るのを防ぐためのものです。たとえば、月末に集中してしまう作業を月初から少しずつ行っていくのが業務平準化です。
業務標準化は属人化の解消を目的とし、業務平準化は作業量や負荷の均一化を目指すものです。
DXとの関係性
DXとはデジタルトランスフォーメーション(Digital Transformation)の略であり、AIやIoTなどのデジタル技術の活用により企業価値を高める取り組みのことをいいます。
今は多くの企業がDXに力を入れているので、実施しない場合は競争力の低下や新規ビジネスの可能性を見逃してしまう可能性にもつながる非常に重要なものです。
DXは、業務標準化のためにも欠かせないものと言えるでしょう。業務標準化のためには、ITの導入や業務フローの自動化が必要となり、これらはDXに関する分野です。
デジタルツールやシステムの導入によって、業務標準化がより効率的に行えるようになります。DXを進めながら業務標準化を実践していきましょう。
業務標準化によって得られる効果
業務標準化によってさまざまな効果が得られます。特に業務の品質を均一化できる、業務の効率化につながる、属人化の防止を図れるといった3つが大きな効果です。それぞれ解説します。
業務の品質を均一化できる
業務標準化により各作業の手順や基準が明確に決められるため、業務の担当者によるばらつきが発生しにくくなります。誰が担当しても同じ品質・内容になるので、製品やサービスの信頼性を高めることにもつながるでしょう。
また、マニュアルなどでルールを定めて取り組むことにより、ミスも抑えられるようになります。顧客満足度や社内の評価を安定させる効果も期待できます。
業務の効率化につながる
標準化された業務は無駄な手順や重複が減るため、スムーズに進められるようになります。たとえば、マニュアルなどによって業務の手順や注意点が明確になっていれば、業務上の迷いややり直しの時間が減るため、業務のスピードアップにつながるでしょう。
細かい部分の判断で迷ってしまい、それが蓄積することで大きな時間のロスにつながってしまうことも珍しくありません。
業務標準化の結果をマニュアルなどにまとめておけば、社員教育にも役立ちます。新入社員も迅速に業務を理解できるため、全体の作業時間が短縮されます。
属人化の防止を図れる
業務が特定の人の経験やノウハウに依存する属人化の状態にある場合、業務標準化によって改善が期待できます。作業内容や注意点、ポイントなどの文書化・共有によって、誰でも一定レベルで同様の業務ができるようになるためです。
属人化が起こっていると、担当者が休んだり突然退社してしまったりした場合に対応できなくなる恐れがあります。
属人化を解消することにより、異動や退職などによって従業員が入れ替わる場合も引き継ぎしやすくなるでしょう。
業務標準化の注意点
実際に業務標準化に取り組んでいくにあたり、いくつか注意しておきたいポイントがあります。標準化に向いていない業務が存在することや、従業員のモチベーション低下の可能性があることの2点を理解しておきましょう。
標準化に向いていない業務がある
すべての業務が標準化に向いているわけではありません。総合的に標準化を行おうと無理をする形になったり、逆効果になったりすることがあるので注意しておきましょう。
業務を行うにあたり専門的な知識やスキルが必要で、共有しても全従業員が対応できない業務は、標準化に向きません。
定期的に業務内容が変化し、柔軟に対応しなければならない業務に関しても標準化すると対応が遅れる恐れがあるので注意しましょう。
従業員のモチベーションが下がる可能性がある
標準化により業務の内容や手順が明確になりますが、誰でも同じ方法で実施することになるため、業務に対する意欲に影響を及ぼす可能性があります。自分の工夫や個性を活かしにくくなれば、仕事がつまらないと感じる人も出てきてしまうでしょう。
また、すべてがルールに縛られており、窮屈と感じてしまう可能性もあります。マンネリ化してモチベーションも落ち、従業員が小さな不満を溜め込んでしまう事態に陥らないように対策を講じなければなりません。
業務標準化を進めるための流れ
どのような流れで業務標準化に取り組んでいくのかについて解説します。企業によって実施の仕方は異なるものの、一般的には以下の手順で進めていきましょう。
手順①標準化する目的を明確にする
はじめに、なぜ業務を標準化するのか目的を明確に決めておきます。「属人化を解消したい」「業務効率を上げたい」「品質のばらつきをなくしたい」など、業務標準化を目指す目的は企業によって異なるはずです。
先に目的を明確にしておくことで、標準化の方向性や進め方などをイメージしやすくなります。目的を明確にした上で業務標準化を行っていく部門や業務の対象を検討しましょう。
手順②業務を洗い出して現状を把握する
次に業務を洗い出し、現状について詳しく把握していきます。各業務の大きなカテゴリではなく、その中で行う作業についても洗い出しましょう。
属人化している作業に関しては、いつ誰がどういった形で業務を行っているのか内容だけではなく、手順も含めて見える化していきます。担当者からのヒアリングも大切です。
現在の作業における問題点も確認しておかなければならないので、実際の作業を観察し、具体的な手順や問題点を把握していきましょう。
手順③標準化すべき業務に優先順位をつける
改善が必要と思われる箇所が見つかったら、どこから手をつけていくのか検討していきます。
すべての業務を一度に標準化するのは難しいので、効果が大きい業務や、問題が深刻な業務から優先させるとよいでしょう。
それほど効果は期待できないものの、短時間で取り組めるということで簡単なものばかり優先させてしまうと、本当に改善すべき業務が先送りになってしまうので注意が必要です。
手順④業務を整理する
洗い出した業務の手順やフローを整理し、無駄な作業や重複がないか確認しましょう。正しくはどのような手順で進めるべきなのか作業標準を定めておくと、無駄な作業や流れを変えるべき作業などが見えてくるはずです。
手順⑤マニュアルと業務フローを作成する
誰が読んでもわかりやすいように整理した業務手順をマニュアル化してまとめていきます。業務フローも作成しておくと全体の流れや関係性が視覚的に把握できるようになるので、よりわかりやすいでしょう。
ポイントは、誰でも手順を押さえて理解できるような内容にするということです。
作成したマニュアルやフローは社内で共有し、その情報を必要とする人がいつでも閲覧できる状態にしておくことをおすすめします。
また、業務手順の見直しやルールの追加・変更などが発生する可能性もあるため、必要に応じて更新できるようにしておきましょう。
手順⑥PDCAを実行する
標準化した業務を実際に運用していきます。その後、PDCAで実行と改善を繰り返し、ブラッシュアップしていきましょう。その際、現場の声も確認しながらPDCAサイクルを回していくことが重要です。
実施した施策が効率化につながっていたとしても、現場に大きな不満をもたらしているようでは成功とは言えません。業務が効率的になっても離職率が高まったり、モチベーションが低下したりする可能性があります。
マニュアルやフローを継続的に改善しながら少しずつ標準化の効果を高めていきましょう。
関連記事
「業務を可視化する目的やメリットは?実施する際の手順をチェック」
業務標準化を成功させるためのポイント
施策実施前にチェックしておきたいポイントがあります。以下の5つを確認した上で取り組んでみてください。
ポイント①業務標準化の目的を社内で共有する
業務標準化は個人で行うものではないため、社内全体で協力して取り組む必要があります。早い段階で施策実施の目的を社内で共有しておきましょう。
業務標準化のためには、これまで行ってきた業務内容や手順を変えなければなりません。これは、従業員にとってストレスに感じやすいことと言えるでしょう。
なぜ必要なのか、どの程度の効果を目指すのかなどをしっかり伝えておくことで、従業員からの協力を得やすくなります。強制的に始めてしまうのではなく、意見交換から行うのもよいでしょう。
ポイント②定期的に見直す
一度標準化した業務はそれをひたすら継続するのではなく、業務内容や状況が変われば更新することが求められます。
新しい作業内容や手順が馴染まず、いつの間にか前のやり方に戻ってしまうケースも考えられるので、定期的な確認も必要です。
PDCAによる改善を行い続けると定期的な見直しにつなげやすくなります。
ポイント③長期的な目線で取り組む
業務標準化は効果が現れるまでに時間を要します。施策の効果がすぐに見えなくても、短絡的に失敗と判断せず、継続的に取り組むことが重要です。
継続することで業務の質や効率が少しずつ向上していきます。
また、一度取り組んで終わりにするのではなく、会社の成長や変化に合わせて継続的に取り組むことが大切です。属人化しているポイントがないかを定期的に確認し、標準化が必要と判断された部分については早めに取り組んでいきましょう。
ポイント④ツールを適切に導入する
業務標準化に役立つツールやシステムが多数存在するため、自社の業務内容や目的に合ったものを選定し、導入することが望ましいです。わかりやすい業務フローの管理ができるツールの活用により、効率的な業務標準化が可能です。
ツールの中には優秀ではあるものの複雑で使いこなすまでに時間がかかってしまうものもあります。求めている機能が搭載されているかだけではなく、使いやすさにもこだわって選定してみてください。
業務標準化は継続して行っていくことになるので、長期的に活用できるか、更新が必要になったときに対応しやすいかも含めて導入するツールを検討しましょう。
ポイント⑤コンサルティングサービスを活用する
初めて業務標準化に取り組む場合は、何から手をつけるべきなのかわからないこともあるでしょう。無理に自社だけで実践しようと考えると失敗してしまう可能性もあります。
そこで、コンサルティングサービスの活用も検討してみてはいかがでしょうか。第三者の視点から業務を分析し、客観的な意見を伝えてもらえます。また、専門的な目線でアドバイスが受けられるのも大きなポイントです。
社内リソースを他の業務に充てられるようになるため、人手不足のため業務標準化に取り組めないと悩んでいる場合も検討しやすくなるでしょう。
業務標準化で得られる効果は多々ある
いかがだったでしょうか。業務標準化とは何か、どのような効果が得られるのかなどについて解説しました。
実施するにあたり押さえておきたいポイントについてご理解いただけたと思います。
能力によるばらつきを減らし、効率化や品質向上を目指すためにも重要な取り組みなので、積極的に実施していくとよいでしょう。
その際には、業務マニュアルを整備しながら業務の標準化を進めていくことをおすすめします。ただ、マニュアル作成には専門的な知識が必要になることから、自社で対応が難しいケースもあるのではないでしょうか。
フィンテックスでは業務の見える化や標準化も含めた業務マニュアル整備を得意としています。現場で本当に役立ち、使いやすいマニュアルを作成したい方はぜひご相談ください。
監修者

企画営業部 営業本部長 / 経営学修士(MBA)
<略歴>
フィンテックスにて、マニュアル作成に関する様々な顧客課題解決に従事。
金融系からエンターテインメント系まで様々な経験から幅広い業務知識を得て、「分かりやすいマニュアル」のあるべき姿を提示。500社以上のマニュアル作成に携わる。また、複数の大企業でマニュアル作成プロジェクトの外部マネージャーを兼務している。
趣味は茶道。
月刊エコノミスト・ビジネスクロニクルで取材していただきました。ぜひご覧ください。
https://business-chronicle.com/person/fintecs.php
マニュアルアカデミー
最新コンテンツ

金融業務マニュアル作成のポイントと制作事例を紹介
2025.12.26
マニュアルのご相談・お問い合わせ
マニュアル作成に関するご相談やお悩みがございましたら、お気軽にお問い合わせください。
-
24時間受付中!
翌営業日にご連絡いたします。 -
資料を無料配布中!
マニュアル作成のコツを伝授します。








