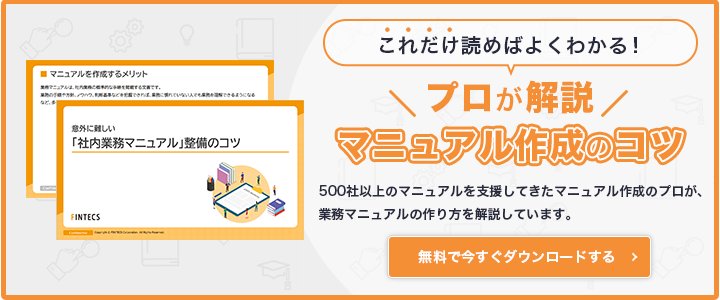-
平日9:00-18:00
- mail お問い合わせ
マニュアルアカデミー
- ホーム
- マニュアルアカデミー
- リスキリング導入のポイントを解説!デジタル人材の育成に向けて
リスキリング導入のポイントを解説!デジタル人材の育成に向けて
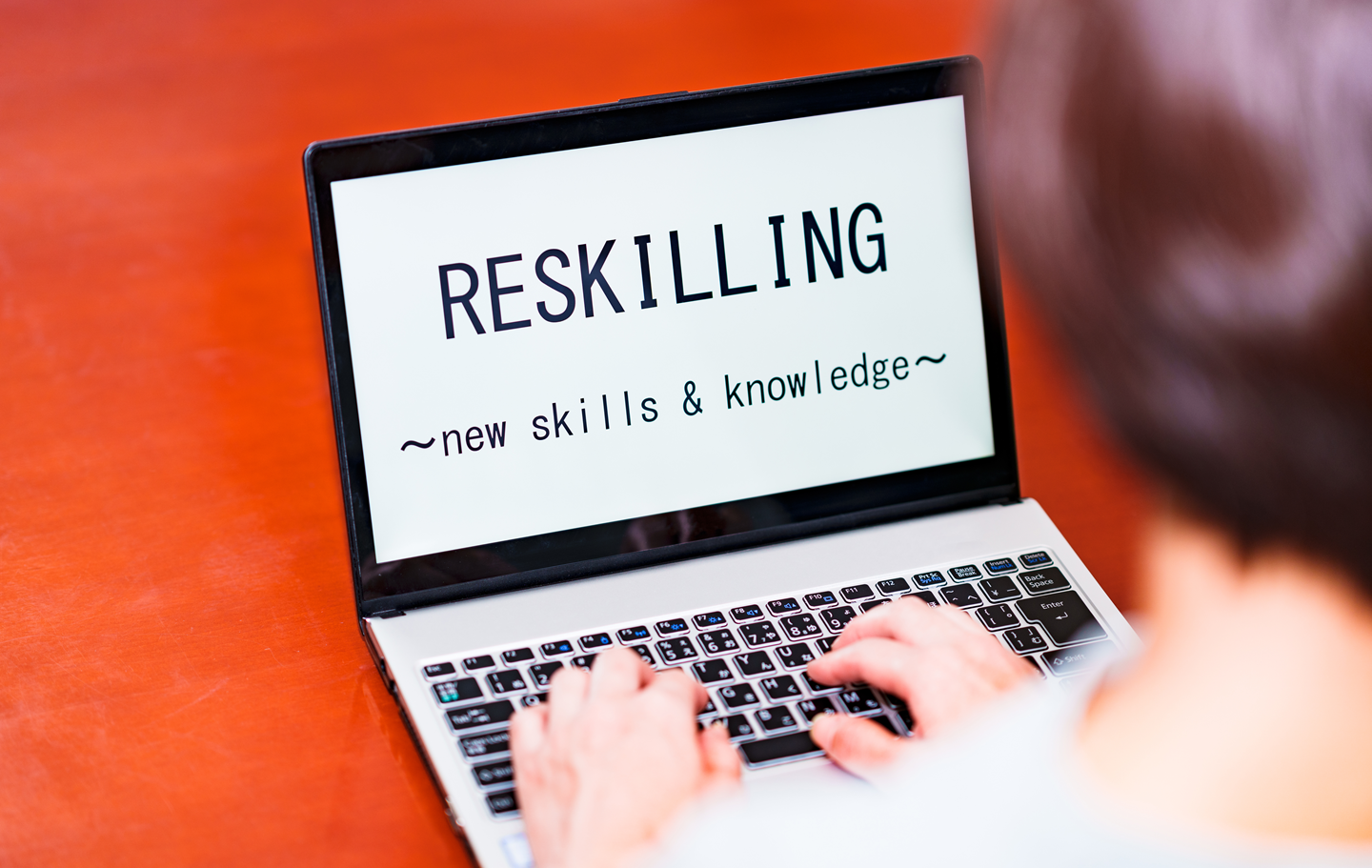
近年、デジタル化の加速や業務の高度化により、企業では従業員のスキルの見直しが急務となっています。その中でも注目されているのが「リスキリング」です。業務内容や職種が変化するなかで、新しいスキルを身につけることで、企業と従業員の両方が変化に対応できるようになります。
この記事では、リスキリングの基本的な考え方から、導入のポイント、成功させるための工夫までをわかりやすく解説します。これからリスキリングに取り組もうと考えている方や、社内教育・人材育成の方法を見直したい人事担当者にとって、ヒントとなる内容をまとめています。
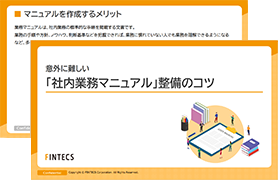
プロが解説!マニュアル作成のコツ
500社以上のマニュアルを支援してきたマニュアル作成のプロが業務マニュアルの作り方を解説しています。
目次
リスキリングとは何か
デジタル人材育成におけるリスキリングの重要性
リスキリング導入のポイント
リスキリングを成功させるための工夫
まとめ
リスキリングとは何か
社会や技術の変化に対応するために、新たなスキルを習得する「リスキリング」。ここではその定義や背景、混同されやすい言葉との違いについて整理します。
リスキリングの定義と意味
リスキリングとは、現在の職務とは異なる業務に就くために、新たなスキルを身につける取り組みのことです。単なるスキル追加ではなく、業務内容の変化を前提とした再教育を意味します。
たとえば、製造業の従業員がAIを活用した品質管理の業務に移る、営業職がデータ分析を担うマーケティング職に転向する、といった例が該当します。企業の競争環境やテクノロジーの進化により、このような人材の再配置の重要性が増しています。
リスキリングが注目されている理由
リスキリングが注目される背景には、デジタル技術の進展と、それに伴う業務内容の変化があります。自動化やデータ活用が進むことで、これまでのスキルだけでは対応できない場面が増えています。
また、人手不足や働き方改革への対応として、社内人材を有効に活用する動きが広がっています。新たな採用よりも、既存の人材が新スキルを得ることで戦力となるケースも多く、コストや時間の面でも合理的です。こうした流れから、政府もリスキリング支援を強化*しています。
*参照:経済産業省 リスキリングを通じたキャリアアップ支援事業
アップスキリングとの違い
リスキリングと混同されやすいのが「アップスキリング」です。アップスキリングは、現在の職務に必要なスキルをさらに高めることを指します。たとえば、営業職がプレゼン力を磨く、IT担当が新しい言語を学ぶといった例です。
一方、リスキリングは「職務の変更」を前提としており、学ぶ内容の幅や深さが異なります。この違いを理解した上で、今後社内でどういった人材が必要になってくるのか、アップスキリングとリスキングのいずれが適しているのかを検討します。現場の声を聞いたりトレンドをリサーチしたりすることで、自社にとって何が必要なのかが明確になり、適切な人材育成の方向性が決まりやすくなります。
デジタル人材育成におけるリスキリングの重要性
企業が持続的に成長するためには、デジタル化に対応できる人材の育成が欠かせません。ここでは、リスキリングがなぜデジタル人材育成において重要なのかを、背景や求められるスキルとともに解説します。
デジタル技術の進化による人材ニーズの変化
AIやクラウド、データ活用などの技術進化により、企業の業務そのものが大きく変わりつつあります。効率化や自動化が進む一方で、それに対応できる人材の確保が課題となっています。
従来のスキルでは対応しきれない場面も多く、社内人材をデジタル対応人材へ育てるリスキリングの必要性が高まっています。今では、単なる教育施策ではなく、企業の変革を支える戦略として位置づけられています。
リスキリングで求められるスキルとは
デジタル人材に求められるのは、技術スキルと柔軟な思考の両方です。たとえば以下のようなスキルがあります。
- データ分析やBIツールの活用
- クラウドやシステムの基本知識
- 新ツールへの対応力やITリテラシー
- DX施策への理解と業務設計力
こうしたスキルは、IT部門に限らず、営業や人事などあらゆる部門で必要とされています。一人ひとりが業務のなかでデジタルを活用できることが、企業力の底上げにつながります。
組織における学習文化の重要性
リスキリングは個人の努力だけでは定着しません。継続的に学び合う文化や挑戦を後押しする職場の雰囲気があってこそ、成果につながります。
制度や教材を整備するだけでなく、成功事例の共有や、従業員の努力や成果に応える仕組みなども大切です。学ぶ意識が自然に根づく環境づくりが、リスキリングの定着には不可欠です。
リスキリング導入のポイント
リスキリングは計画的に進めることで、より効果的な成果につながります。この章では、導入時に押さえておきたい基本的なポイントを紹介します。
現状スキルの可視化と課題の把握
まず重要なのは、従業員が現在どのようなスキルを持っているかを把握することです。どの分野に強みがあり、何が不足しているかを明確にすると、学習目標が立てやすくなります。
業務棚卸しやスキルアップ作成を行えば、部署や個人ごとのスキル状況を把握でき、組織としての課題共有にも役立ちます。あわせて、従業員の希望や不安のヒアリングも効果的です。
育成対象と優先順位の明確化
リスキリングは、全員一律で行うよりも、段階的かつ重点的に進める方が効果的です。たとえば、DX推進部門や変革を担う職種から始めるなど、優先順位を明確にしましょう。
対象やスケジュール、目標を定めて進めれば、現場への負担も抑えられ、継続しやすくなります。限られたリソースで成果を上げるためには、戦略的な設計が大切です。
教育コンテンツやプログラムの整備
学ぶための教材や仕組みが整っていることも重要です。オンライン学習、外部研修、社内講座などを組み合わせると、より柔軟な学習環境がつくれます。
マニュアルや動画などの社内教材を活用することで、業務と連携した実践的な学びが可能になります。
関連記事
「新人教育のポイントとは?大切な6つのポイントと有効な手段」
社内共有・動機付けの仕組みづくり
どれだけ制度が整っていても、従業員の参加意欲がなければリスキリングは進みません。そのため、取り組む意義やメリットを社内でしっかり共有することが大切です。
キャリア形成や成長のチャンスにつながることを伝え、動機付けを行いましょう。社内報での紹介や事例共有など、継続的な発信も効果的です。
リスキリングを成功させるための工夫
実施後のフォローや職場での定着まで考えることが、リスキングの成功の鍵です。
この章では、効果を出すための工夫や現場に根づかせるポイントをご紹介します。
継続的なフォローとスキル評価
一度学んで終わりではなく、定期的な振り返りやスキルチェックを行うことで、習得状況の確認とモチベーション維持ができます。
また、スキルの成長を評価に反映させることで、学ぶ意欲を高めることにもつながります。小さな成果もきちんと認めることが、学習を続ける支えになります。
マニュアルやナレッジの整備による定着支援
新しい知識を実際の業務に活かすには、マニュアルやナレッジの整備が効果的です。具体的な手順を文書化することで、業務での実践がスムーズになります。
たとえば、ツールの操作マニュアルやチェックリストを用意することで、学習内容が業務のなかで活用しやすくなります。
社内DXと連携した仕組み化の推進
リスキリングを成果に結びつけるには、社内DXと連動させることが重要です。スキルを活かせる業務環境を整えることで、学びが実際の仕事に結びつきます。
たとえば、業務プロセスの見直しと合わせてツールを刷新し、学んだスキルを使う機会を設けるなど、仕組みづくりがポイントです。人材育成と業務改善が連動すれば、組織の成長にもつながります。
まとめ
リスキリングは、変化の激しい社会やビジネス環境に対応するための重要な取り組みです。特にデジタル技術の進化により、従業員一人ひとりに求められるスキルも大きく変わってきています。
導入を成功させるには、現状のスキルの把握や優先順位の整理、学習環境の整備が欠かせません。加えて、学びを定着させる仕組みや、組織としての支援体制づくりも重要です。
マニュアルやナレッジの整備は、学びを実務に活かすための強力なツールになります。フィンテックスでは、こうした社内のナレッジ定着支援に向けたマニュアル作成や業務可視化のご相談も承っています。興味をお持ちの方はぜひお問い合わせください。
フィンテックスでは各種業務マニュアルの作成を行っているので、ぜひご相談ください。
監修者

企画営業部 営業本部長 / 経営学修士(MBA)
<略歴>
フィンテックスにて、マニュアル作成に関する様々な顧客課題解決に従事。
金融系からエンターテインメント系まで様々な経験から幅広い業務知識を得て、「分かりやすいマニュアル」のあるべき姿を提示。500社以上のマニュアル作成に携わる。また、複数の大企業でマニュアル作成プロジェクトの外部マネージャーを兼務している。
趣味は茶道。
月刊エコノミスト・ビジネスクロニクルで取材していただきました。ぜひご覧ください。
https://business-chronicle.com/person/fintecs.php
マニュアルアカデミー
最新コンテンツ

金融業務マニュアル作成のポイントと制作事例を紹介
2025.12.26
マニュアルのご相談・お問い合わせ
マニュアル作成に関するご相談やお悩みがございましたら、お気軽にお問い合わせください。
-
24時間受付中!
翌営業日にご連絡いたします。 -
資料を無料配布中!
マニュアル作成のコツを伝授します。