-
平日9:00-18:00
- mail お問い合わせ
マニュアルアカデミー
- ホーム
- マニュアルアカデミー
- 心理的安全性とは?組織の中での作り方のポイントや注意点を解説
心理的安全性とは?組織の中での作り方のポイントや注意点を解説

職場で「本音が言える空気」があるかどうかは、チームの成果や働きやすさに大きく関わります。こうした環境づくりのカギとなるのが「心理的安全性」です。近年では、大手企業をはじめ多くの組織でこの考え方が注目され、働き方改革や組織づくりの中心テーマにもなっています。
本記事では、心理的安全性の基本から、職場で高めるための実践ポイント、注意点までをわかりやすく解説します。あわせて、業務の進め方やルールを明確にすることが心理的な安心にどう影響するかについても簡単にご紹介します。チームの力を引き出す環境づくりを考える方は、ぜひ参考にしてみてください。
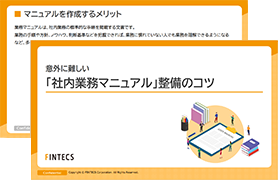
プロが解説!マニュアル作成のコツ
500社以上のマニュアルを支援してきたマニュアル作成のプロが業務マニュアルの作り方を解説しています。
目次
心理的安全性とは何か
心理的安全性を高めるためのポイント
心理的安全性を確保するうえでの注意点
心理的安全性と業務環境づくりの関係
まとめ
心理的安全性とは何か
心理的安全性とは、組織やチームの中で一人ひとりが自分の意見や気持ちを安心して表現できる状態のことを指します。たとえミスや意見の相違があっても、非難や不当な評価を受けず、尊重される職場環境が「心理的に安全な状態」といえます。この安心感が、信頼関係を育み、業務効率や改善力にもつながっていきます。
心理的安全性の定義
心理的安全性は、アメリカの組織行動学者エイミー・エドモンドソン氏によって提唱された概念です。職場で「自分の考えや疑問を伝えても大丈夫」と思えることが、チームの創造性や成長の促進に寄与するとされています。
注目されるようになった背景
心理的安全性が注目されるようになった背景には、2012年から約4年間かけて実施されたGoogleの「プロジェクト・アリストテレス」があります。この研究では、高パフォーマンスなチームに共通する最も重要な要素が心理的安全性であると明らかになり、国内外で注目が集まりました。
心理的安全性が高い組織の特徴
心理的安全性が高い組織には、次のような特徴があります。
- 失敗しても責められない文化がある
- リーダーが自ら開示し、対話が活発
- 多様な意見や価値観が認められている
- 疑問をすぐに共有しやすい雰囲気がある
こうした職場では、柔軟な発想や改善につながる取り組みが生まれやすくなります。
心理的安全性と業績・離職率の関係
心理的安全性の高さは、業績や社員の定着にも影響します。安心して発言できる職場では、ミスの早期発見や情報共有が進み、チーム全体のパフォーマンスが高まります。一方で、安全性が低い環境では発言が抑えられ、課題が放置されるなどのリスクが増し、離職にもつながる恐れがあります。
心理的安全性を高めるためのポイント
心理的安全性は、日々のコミュニケーションやチーム運営の工夫で少しずつ育まれていきます。大がかりな改革を行わなくても、身近な行動の積み重ねが信頼関係を強化し、職場の空気をより安心できるものへと変えていきます。ここでは、具体的な実践ポイントを紹介します。
上司・リーダーの姿勢
心理的安全性の基盤をつくるには、上司やリーダーの姿勢が重要です。自らの意見やミスを率直に共有し、部下の話に耳を傾ける姿勢を見せることで、安心して発言できる雰囲気が生まれます。否定から入らず、まず受け止める姿勢を心がけることが信頼構築につながります。
メンバー同士の信頼関係の構築
メンバー間の信頼関係があると、心理的安全性は自然と高まります。業務内外の会話を通じてお互いを知り、協力し合える土台ができます。雑談や小さな声かけなど、日常のふれあいが大切です。一人ひとり が受け入れられていると感じられる雰囲気づくりを目指しましょう。
フィードバックと意見交換の機会
定期的なフィードバックは、安心して意見を交わせる職場づくりに効果的です。相手の意見に「ありがとう」や「参考になった」と応えることで、ポジティブな対話が生まれます。活発な意見交換が行われることで、協力体制や改善意識も育ちます。
ミスを許容する文化の醸成
ミスを過度に責める文化は、発言や行動の萎縮を招きます。「誰にでもミスはある」と認識を共有し、原因の共有と改善に焦点を当てることが大切です。安心して挑戦できる環境は、組織の成長にもつながります。
新入社員が安心して働き始められる環境づくり
新入社員は、特に不安や緊張を抱きやすいものです。だからこそ、心理的安全性は入社直後から意識したいポイントです。新入社員が業務に不安なく取り組めるよう、マニュアルや相談できる体制を整えると安心感が生まれます。質問しやすい雰囲気があれば、早期離職の防止にも役立ちます。
心理的安全性を確保するうえでの注意点
心理的安全性を高める取り組みは組織にとって有効ですが、進め方を誤ると逆効果になることもあります。意図せずメンバーに負担をかけてしまったり、誤解から不公平感を生んだりすることがあるため、慎重な対応が求められます。ここでは、取り組みの際に意識しておきたい注意点をご紹介します。
意見の「押し付け」にならないようにする
意見を出しやすい場をつくることは重要ですが、全員に発言を求めすぎると、かえって負担になることもあります。「発言しない自由」も大切にし、それぞれの性格やスタンスに配慮した対応が求められます。強制よりも自然な流れを大切にしてください。
無理に仲良くさせようとしない
心理的安全性は、「仲のよさ」そのものではありません。無理に親密な関係を築かせようとすると、かえってストレスを感じることがあります。業務上の信頼があれば、過度な距離の近さは必要ありません。適度な関係性が心理的に安心できる場合もあります。
公平性と透明性を保つ
特定のメンバーにだけ情報が集まる、評価が不明確といった状態は、不信感を生みます。評価やルールの運用においては、透明性と公平性を保つことが重要です。チーム全体が納得できるようなルールや運用体制を整えてください。
心理的安全性と甘やかしを混同しない
心理的安全性を「何をしても許される」と捉えてしまうと、組織の規律が乱れます。発言や挑戦を受け入れる姿勢と、業務上の責任を果たすことは両立すべきものです。健全なルールの中でこそ、心理的な安心感は持続できます。
心理的安全性と業務環境づくりの関係
心理的安全性を高めるうえで、コミュニケーションや人間関係の工夫が注目されがちですが、実は「業務環境の整備」も見逃せない要素です。とくに、業務のやり方や役割があいまいな状態では、メンバーの不安やストレスが高まりやすくなります。ここでは、明確なルールや仕組みを整えることが、心理的な安心感の向上にどうつながるのかを簡潔にご紹介します。
明確な業務手順が安心感を生む
業務の流れや判断基準が明文化されていないと、何をどう進めればよいのかがわからず、不安を感じやすくなります。手順や対応方法をマニュアルなどで明確にしておくことで、仕事の進め方に迷いがなくなり、安心して業務に取り組めるようになります。
関連記事
「わかりやすいマニュアルを書くための文章作成ガイド」
属人化を防ぎ、不安を減らす
「この作業はあの人にしかできない」といった属人化があると、業務が滞ったり、業務上の負荷が偏ったりする原因になります。業務内容を共有・整備しておくことで、特定の人に依存しない体制がつくられ、チーム全体の心理的な余裕にもつながります。
新人や異動者の不安軽減に役立つ
新しく配属されたメンバーは、業務の進め方や職場のルールがわからず、不安を抱えやすいものです。業務の基本やルールがあらかじめ整っていることで、スムーズに馴染むことができ、心理的な安心感も得られます。
チーム内での共通理解を深める
業務の進め方や判断基準を共有しておくことで、メンバー間の認識のズレを防ぐことができます。共通の理解があることで、不要な衝突や誤解が減り、安心して意見を交わせる空気も生まれやすくなります。
まとめ
心理的安全性とは、一人ひとり が安心して意見を伝えられる環境のことです。近年はその重要性が広く認識され、チームのパフォーマンス向上や離職防止にもつながるとして、多くの企業で注目されています。
心理的安全性を高めるには、上司の姿勢やメンバー間の信頼、日常的な対話など、日々の積み重ねが大切です。また、業務の進め方やルールを明確にしておくことも、安心して働ける職場づくりの一助になります。業務環境の整備も、心理的安全性を高めるための重要なポイントになるため、検討してみてはいかがでしょうか。
フィンテックスでは、業務マニュアルの作成を通じて、業務環境整備のお手伝いをしています。業務の体系整理やマニュアル整備が必要な場合はぜひお問合わせください。
フィンテックスでは各種業務マニュアルの作成を行っているので、ぜひご相談ください。
監修者

企画営業部 営業本部長 / 経営学修士(MBA)
<略歴>
フィンテックスにて、マニュアル作成に関する様々な顧客課題解決に従事。
金融系からエンターテインメント系まで様々な経験から幅広い業務知識を得て、「分かりやすいマニュアル」のあるべき姿を提示。500社以上のマニュアル作成に携わる。また、複数の大企業でマニュアル作成プロジェクトの外部マネージャーを兼務している。
趣味は茶道。
月刊エコノミスト・ビジネスクロニクルで取材していただきました。ぜひご覧ください。
https://business-chronicle.com/person/fintecs.php
マニュアルアカデミー
最新コンテンツ

金融業務マニュアル作成のポイントと制作事例を紹介
2025.12.26
マニュアルのご相談・お問い合わせ
マニュアル作成に関するご相談やお悩みがございましたら、お気軽にお問い合わせください。
-
24時間受付中!
翌営業日にご連絡いたします。 -
資料を無料配布中!
マニュアル作成のコツを伝授します。








