-
平日9:00-18:00
- mail お問い合わせ
マニュアルアカデミー
- ホーム
- マニュアルアカデミー
- 業務改善プロジェクトの進め方と効果を引き出す5つのポイント
業務改善プロジェクトの進め方と効果を引き出す5つのポイント

業務改善プロジェクトを成功させるためには、事前にしっかりと準備を行い、計画した業務改善プロジェクトを着実に進めていくことが重要です。
さらに、効果を高めるためには工夫も必要となりますが、具体的な進め方がわからず悩んでいる方もいるでしょう。
この記事では、業務改善プロジェクトの具体的な進め方とコツについて解説します。
この記事を読むことで、業務改善プロジェクトの全体のステップや、実際に役立つツールについて理解を深められます。ぜひご覧ください。
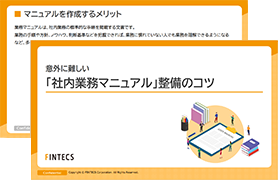
プロが解説!マニュアル作成のコツ
500社以上のマニュアルを支援してきたマニュアル作成のプロが業務マニュアルの作り方を解説しています。
目次
業務改善とは
業務改善プロジェクトの前に準備すべきこと
業務改善プロジェクトの進め方
業務改善の効果を引き出すポイント
業務改善プロジェクトで活用できるツール
業務改善プロジェクトは長い目で実践していくことが大切
業務改善とは
そもそも、業務改善とは何かというと、企業や組織が日々の業務の中で抱えている課題や非効率な部分を洗い出し、効率的に改善していくための仕組みや取り組みです。
業務時間を短縮するためには、現在の作業を削減する方法もありますが、それだけでは他の部分に支障が出る可能性があり、必ずしも業務改善にはつながるわけではありません。
単なる作業の削減ではなく、従業員の負担軽減や顧客満足度の向上につながる業務内容の改善が重要です。企業が実践すべき業務の内容や、重点的に改善すべきポイントは時代とともに変化していきます。
そのため、企業や組織が持続的に成長するためにも、業務改善は欠かせません。
業務改善プロジェクトの前に準備すべきこと
実際に業務改善プロジェクトに取り組もうと考えた際は、事前準備が成功を左右します。
ここでは、事前準備として行っておきたい「目的と目標の明確化」と「課題点の想定」について解説します。
目的と目標を明確にする
まず、業務改善プロジェクトを行う目的と目標を明確にしておきましょう。これは、プロジェクトに関わる人すべてが共通認識を持つためにも欠かせません。
全体としてのゴールである目的・目標を明確にしておくことで、どのように取り組めばよいのかイメージしやすくなります。 また、途中で方針や改善案がぶれてしまうこともなくなるはずです。
たとえば、具体的に目的・目標を定めることなく「無駄な業務を削除する」と考えるよりも、「月の残業時間を◯時間減らす」と考えた方が具体的な対策が見えてきます。
目的と目標を定める際は、達成を目指すまでの期限を設けておくことも重要です。また、各作業の担当者や目標値もあわせて検討しておきましょう。
課題点を想定しておく
目的・目標の達成を目指して取り組んでいくためには、改善すべきポイントを明確にしておくことも欠かせません。目的・目標達成のためにどのようなことが課題になっているのかをひとつひとつ話し合って明らかにしていきます。
このとき、誤った推測をしてしまうと業務改善が遠回りになってしまうこともあるため、個人で判断せず、課題の内容を全体で話し合うことが重要です。推測で当たりをつけた後に、業務改善の対象となる課題をより明確に探っていきましょう。
たとえば、本来であれば必要ないはずの無駄な作業が発生している、コミュニケーションがうまくいっていないなどの課題を見つけておくと、改善すべきポイントを把握できます。
業務改善プロジェクトの進め方
目的・目標を明確にし、課題点の想定まで実践できたら、業務改善プロジェクトを進行していくことになります。その際は、以下6つのステップを踏んで進めていきましょう。
手順①現状の業務量を把握する
現状の業務量を把握することは、業務改善を効率的に進める上で重要な作業です。全体の業務量が曖昧なままで業務改善に取り掛かると、改善の必要がない部分に無駄な労力を割いてしまう可能性があります。
業務量を把握することにより、時間やコストがかかっている作業を見つけられるようになるため、改善が必要なポイントを判断できます。業務量を把握する方法にはいくつかの方法があり、それぞれ特徴や適したケースが異なるので、確認しておきましょう。
ここでは、4つの方法について解説します。
方法①実測法
実測法とは、実際の業務を観測しながら現状の業務量を調査する方法のことです。
観測を担当する人を選び、現場のモニタリングから始めましょう。実際に行われている作業を確認した上で業務量を判断することになるので、情報の信頼性が高いというメリットがあります。
しかし、計測に手間がかかることから、対象業務が多い場合は担当する観測者に負担がかかってしまう可能性があるのはデメリットです。条件や作業者が変わっても業務に必要な時間が大きく変わらない、誰が行っても作業時間にブレが発生しにくいルーチン業務の計測に適した方法といえます。
方法②実績記入法
実績記入法は、実際に作業を行った担当者に各業務にかかった時間を記入してもらう方法です。自己申告となるため、データの信頼性が必ずしも高いとは限らない点に注意が必要です。
たとえば、記録忘れなどによって後から「確かメールの対応は10分程度で済んだはず」と曖昧な報告となってしまえば、全体的なずれが大きく出てしまうことも考えられます。
しかし、実績記入法は実測法と異なり、観測者が現場のモニタリングを行う必要がありません。同時に複数の現場の業務量調査を行いやすく、限られた担当者に負担が集中しにくいのはメリットといえるでしょう。
ひとつひとつの業務にかかる時間を正確に調査したいというよりも、大まかに把握したい場合に向いている方法です。
方法③推定比率法
推定比率法は、作業者やマネージャーなどの担当者が全体の業務時間から逆算する形で業務量を推測する方法のことです。
実測法や実績記入法と比較すると正確性には欠けますが、各実績を記入する時間がかからないことからスピーディーな調査結果を得られるのが特徴です。
大きな課題があって早急に改善に取り組む必要があり、迅速に全体の業務量を把握したい場合に適しています。しかし、記入者の主観に頼る部分が大きいことから、推定比率法には記入者によってばらつきが発生しやすいデメリットがあることを確認しておきましょう。
はじめに推定比率法を用いて全体の業務量を概略として把握し、その後に実測法で詳細を確認する方法もあります。
方法④合成法
合成法とは、ここまで紹介した3つの方法のうち、いくつかを組み合わせて業務量をより正確に把握する手法のことです。たとえば、作業を行った担当者が自ら記入を行う実績記入法と、観測者が現場を観察する実測法とを組み合わせることで、それぞれの方法で生じる誤差を緩和することも可能です。
複数の業務量分析を行うことから時間と手間がかかりますが、特に詳細にデータの集計と分析を行わなければならないケースに適しています。
手順②業務フロー図を作成する
業務量を把握した後、業務フロー図を作成して日常業務の流れを可視化していきましょう。業務フロー図とは、業務の流れや各作業手順を図で表したものです。
業務フロー図を作成することでどの工程に時間がかかっているのか、どの部分に無駄や重複が発生しているのかを判断することが可能です。業務フロー図を複数人で作成する場合は、関係者全員が共通ルールを守る必要があります。ルールが曖昧だと認識のズレが生じる可能性があるため注意してください。
この後に課題点を書き出す作業を行うことになるのですが、その際にも業務フロー図が必要です。そのため、丁寧に作成しておくことが求められます。
関連記事
「業務を可視化する目的やメリットは?実施する際の手順をチェック」
手順③課題点を書き出す
業務フロー図の作成が完了したら、次は課題点を洗い出します。
業務改善を行う際は、どこに問題があるのかを正しく把握することが欠かせません。ここが失敗してしまうと的外れの改善策になってしまうこともあります。
課題点を見つける際は、必要以上に時間がかかっている部分や、確認作業の重複、情報共有に問題がある部分などを探し出すことがポイントです。
課題点の洗い出しは1人の担当者ではなく、関係者全員で行うことが望ましいです。
この段階では直接的な解決策を考える必要はありません。それぞれが気づいた課題を具体的に書き出していきます。
手順④課題点の改善案を立てる
洗い出した課題点に対し、それぞれ改善策を立てていきます。課題が以下のどれに該当するかを明確にした上で、改善策を立てると効果的です。
【課題改善に向けた選択肢】
- 廃止する:昔は必要だった業務だが現在は不必要な業務は、廃止することで業務時間の削減につながる
- 標準化する:作業者によって手順や時間、品質にバラつきがある業務はマニュアルを作成するなどして標準化する
- 導入:新たな手順やツールを取り入れたり、他のシステムと入れ替えたりすることで改善を図る
不要な業務の廃止は比較的簡単に実施できますが、導入は新たなシステムや仕組みを取り入れる必要があり、他の業務への影響も大きいため、慎重な検討が求められます。
手順⑤改善案を実践する
実際に現場で改善策を実行していきます。課題を洗い出す際、複数の課題が見つかることもあるでしょう。
しかし、一度にすべてを変えると対応が難しくなってしまうため、優先度が高く、小規模で始められるものから取り組んでいくと効果的です。
実際に着手してみると、想定していた通りに改善策を進められないこともあります。そのため、適時柔軟に対応していかなければなりません。
進捗確認には、目標達成までの各プロセスの達成度合いを計測・監視するKPI(Key Performance Indicator:重要業績評価指標)を用いるとよいでしょう。
KPIで目標達成までのギャップを明らかにすることで何をすべきかが明確になり、効率よく目標達成を目指しやすくなります。
手順⑥効果を測定してPDCAサイクルを回す
改善策を実施したらそれで終わりにしてしまうのではなく、一連の業務を振り返り、問題点を確認した上で、業務プロセスの改善を重ねていくことが重要です。
「Plan(計画)」「Do(実行)」「Check(評価)」「Action(改善)」の頭文字をとって名付けられた業務改善に関するフレームワークである「PDCAサイクル」を実施していきましょう。
日々の業務を継続していく中で新しい課題が見つかることも少なくありません。そういった場合も、継続してPDCAサイクルを回していくことでよりよい組織を目指していくことができます。
業務改善の効果を引き出すポイント
突然業務改善に取り組もうとしても、なかなか十分な効果を引き出すことはできません。効果を高めるためには、押さえておきたいポイントがいくつかあります。
ここでは、特に重視したいポイントを5つ解説します。
ポイント①プロジェクトの実施体制を構築する
まずは、プロジェクトの実施体制を構築することから始めましょう。そのためには、プロジェクトを統括する立場であるマネージャーの選出が必要です。
マネージャーには、プロジェクトの進捗・課題・リスク管理を行う重要な役割もあります。そのため、特に慎重に検討しなければなりません。
次に、プロジェクトの参加メンバーを決めていきましょう。プロジェクトチームメンバーには現場の担当者を入れることで、実際の課題やニーズを把握しやすくなります。
また、重要な課題に対する対策を判断する意思決定機関を設けておくことも大切です。
業務改善プロジェクトについては、社内でしっかりと周知することも重要です。さまざまな部門に協力を依頼する場合もあるため、プロジェクト体制を明確に伝えておくことで、協力を得やすくなります。
ポイント②効果の測定と分析を継続的に行う
業務改善を行った後の効果測定と分析は継続的に行うことが重要です。その際はPDCAサイクルを使うことで効率的な改善につながります。
行う業務内容が変わった場合や、新しいシステムを導入した場合なども業務プロセスに対して継続的な改善を図るようにしましょう。
よくあるのが、改善策を実施しても、その効果を確認することなく成果がわからない状況に陥ってしまうことです。
事前に設定した指標に基づいて効果測定を行います。
その際「残業時間がどの程度削減できたか」など、数値で評価できるものだとよりわかりやすいでしょう。
想定していた成果につながっていない場合は改善方法を修正してから再度業務改善を実践します。これらを繰り返すことにより効率よく業務改善につなげることが可能です。
ポイント③進捗状況を共有する
関係者に対して定期的に進捗状況を共有することで、メンバーが現在の状況を把握しやすくなります。
このような状況を作ることで、各メンバーが自分に求められていることや行わなければならないことを理解できるようになるので、協力しやすくなるでしょう。
進捗が共有されプロジェクトが進んでいることや効果が出ていることがわかれば、関係者のモチベーション向上にもつながります。
どのような形で進捗の共有を行うのかについても早い段階で決めておくことが重要です。難しい方法や手間がかかる方法だと進捗の共有が後回しになってしまうこともあるため、注意しましょう。
ポイント④改善案を見直して適宜修正する
一度立てた改善案を実際に行ってみたところ、修正や変更が必要になることもあります。そのため、定期的に改善案を見直し、必要に応じて改善案に対応することが重要です。
「何が何でも計画通りに進めよう」「決めた通りに取り組めばうまくいくはず」といった考え方を捨て、柔軟に改善案を見直して修正することで、より効果的な業務改善につなげることができます。
ポイント⑤スモールスタートで実施する
いきなり大規模に業務改善プロジェクトを始めるのではなく、小規模から試すスモールスタートをおすすめします。
はじめから広範囲にプロジェクトを実施しようとすると現場負担や混乱が大きくなってしまう可能性もあるためです。
まずは「やってみる」という姿勢で、小さな成功を積み重ねていき、大きな成果へとつなげましょう。仮に失敗した場合にリスクが大きい業務については、スモールスタートで実施することが欠かせません。
業務改善プロジェクトで活用できるツール
業務改善プロジェクトを成功させるためには、計画立案から実行・定着までを効率的に行うための各種ツールを活用していくのがおすすめです。
ツールを活用することで、従来の手作業では時間がかかっていた部分を効率化できたり、進捗管理が容易になったりします。
ここでは、業務改善プロジェクトを進める上で役立つ主なツールを2つ紹介します。
進捗管理ツール
プロジェクト全体の進み具合を可視化するために活躍するのが、進捗管理ツールです。業務改善を進めていくにあたり、複数の課題解決を同時に目指すこともあるでしょう。
しかし、取り組む課題が多くなるほど、どの対策がどこまで進んでいるのかわかりづらくなることがあります。
このような場合も、進捗管理ツールを使用することで各タスクの完了状況や進み具合を一覧で把握できるようになります。
タスク管理・プロジェクト管理・フロー管理のいずれかに特化しているツールもあるので、自社で必要なものを選択しましょう。
ツール導入を任された担当者が独自に決定するのではなく、現場メンバーにとって使いやすいかどうかを重視することも重要です。
マニュアル作成ツール
業務の標準化と効率化を目指すために活用していきたいのが、マニュアル作成ツールです。業務改善ではこれまでとは異なる手順や仕組みを導入することもありますが、これらをしっかりと現場に浸透させることが重要になります。
マニュアル作成ツールを用いることにより、わかりやすく業務手順や各種操作方法を共有できるようになるので、担当者が異なる場合でも同じ水準で作業することが可能です。
特に、属人化している業務については積極的にマニュアルを作成し、担当者が不在でも他のメンバーが対応できる体制を整えましょう。
ExcelやWordでマニュアルを作成することも可能ではありますが、マニュアル作成ツールを活用することで現場担当者に対してよりわかりやすく業務内容・ノウハウを伝えられるようになります。
業務改善プロジェクトは長い目で実践していくことが大切
いかがでしたでしょうか。業務改善プロジェクトの概要や実施内容についてご紹介しました。進め方のコツもご理解いただけたかと思います。
効果を引き出すためには、体制づくりや進捗の共有が欠かせません。その上で、改善後の業務手順を現場に浸透させましょう。
そのためには、マニュアルを活用することをおすすめします。
作業に関するマニュアルを整備することで、誰もが同じ基準で業務を行えるようになり、効率的な業務改善が実現しやすくなります。
フィンテックスではこれまで、ユーザーにとって本当に必要な、役に立つマニュアルの作成を多数サポートしてきました。
当社がこれまで培ってきたノウハウを活かし、マニュアル作成に関する課題の解決をサポートいたします。ぜひご相談ください。
監修者

企画営業部 営業本部長 / 経営学修士(MBA)
<略歴>
フィンテックスにて、マニュアル作成に関する様々な顧客課題解決に従事。
金融系からエンターテインメント系まで様々な経験から幅広い業務知識を得て、「分かりやすいマニュアル」のあるべき姿を提示。500社以上のマニュアル作成に携わる。また、複数の大企業でマニュアル作成プロジェクトの外部マネージャーを兼務している。
趣味は茶道。
月刊エコノミスト・ビジネスクロニクルで取材していただきました。ぜひご覧ください。
https://business-chronicle.com/person/fintecs.php
マニュアルアカデミー
最新コンテンツ

金融業務マニュアル作成のポイントと制作事例を紹介
2025.12.26
マニュアルのご相談・お問い合わせ
マニュアル作成に関するご相談やお悩みがございましたら、お気軽にお問い合わせください。
-
24時間受付中!
翌営業日にご連絡いたします。 -
資料を無料配布中!
マニュアル作成のコツを伝授します。








