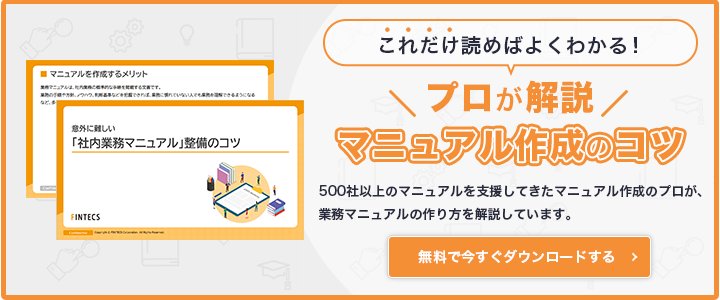-
平日9:00-18:00
- mail お問い合わせ
マニュアルアカデミー
- ホーム
- マニュアルアカデミー
- ヒヤリハットとは?業界ごとの事例や重大事故を未然に防ぐコツを解説
ヒヤリハットとは?業界ごとの事例や重大事故を未然に防ぐコツを解説

業務中に「ヒヤリ」とした経験や「ハッ」と気づいたことはありませんか?
こうした些細な違和感や危険の芽は、重大な事故の前兆であることが多く、どの業界でも見逃せない重要なテーマです。
この記事では、ヒヤリハットの基本的な知識から見逃さないための職場づくり、未然に防ぐための具体策までをわかりやすく解説します。
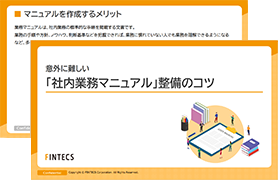
プロが解説!マニュアル作成のコツ
500社以上のマニュアルを支援してきたマニュアル作成のプロが業務マニュアルの作り方を解説しています。
目次
ヒヤリハットとは何か
ヒヤリハットを見逃さない職場環境とは
ヒヤリハットをきっかけに重大事故を防ぐには
まとめ
ヒヤリハットとは何か
ヒヤリハットの本質を知ることで、日常の業務の中に潜むリスクへの感度が高まり、事故の未然防止につながります。まずは基本的な意味や考え方を確認していきましょう。
ヒヤリハットの意味と定義
ヒヤリハットとは、事故や災害には至らなかったものの、一歩間違えば重大な結果を招いていたかもしれない事象のことを指します。「ヒヤリとした」「ハッとした」という感覚から名付けられたこの言葉は、安全管理の分野では古くから使われており、業界を問わずリスクマネジメントの基礎として知られています。
たとえば、倉庫で荷物の積み上げが不安定だったが崩れなかった、医療現場で薬の取り違えに気づいて投与前に止められた、というような状況がヒヤリハットの典型です。これらは実際の事故ではないため記録されないかもしれませんが、見逃さずに捉えることで重大事故の予防につながります。
重大事故とヒヤリハットの関係性(ハインリッヒの法則)
ハインリッヒの法則は、労働災害に関する有名な経験則で、「1つの重大事故の背後には、29の軽微な事故と300のヒヤリハットが存在する」といわれています。この比率からわかるように、ヒヤリハットは見過ごされがちですが、実は事故発生の警告サインでもあります。
ヒヤリハットが見逃され、改善されないままでいると、いずれ重大なトラブルや事故へと発展する可能性があります。日常業務の中での小さな違和感やミスの芽に敏感になることが、事故を未然に防ぐ第一歩となります。
ヒヤリハットが重要である理由
ヒヤリハットは、安全管理の分野で古くから用いられてきた概念であり、働き方や時代が変化してもなお重要視すべき考え方です。
近年では、企業のコンプライアンス強化や、業務の標準化・品質管理の重要性が認識されるようになったことも、ヒヤリハットへの関心を高める要因となっています。
また、労働人口の減少に伴って働き方が多様化し、人材の流動性が高まる中で、一人ひとりの注意力に依存するのではなく、仕組みとしてリスクを予防する体制づくりが求められるようになってきました。その中で、ヒヤリハットの記録や共有、分析と改善といったアプローチが、業務マニュアルやチェックリストとともにますます重要視されています。
ヒヤリハットを見逃さない職場環境とは
ヒヤリハットは気づかれずに放置されると、将来の重大事故につながるリスクがあります。そのためには、単に個人の注意力に頼るのではなく、組織として「気づきやすい」「報告しやすい」「共有しやすい」環境を整えることが重要です。ここでは、そのために必要な視点や仕組みについて解説します。
気づきを促す視点と思考習慣
ヒヤリハットに気づくには、「これは危なかったかもしれない」と感じ取れる視点や感覚が必要です。日々の業務の中で次のような思考習慣を持つことが、リスクへの感度を高めます。
- なぜこの作業手順になっているのかを考える
- このまま作業を進めたら何が起こる可能性があるかを想像する
- 自分の動作が周囲にどんな影響を与えるか意識する
- 以前にヒヤリとした経験がある場面では特に注意する
- 小さな違和感も「気のせい」にせず、立ち止まって確認する
また、こうした視点を組織全体で共有するために、過去の事例を使ったミーティングや、日常の中での声かけが効果的です。
報告しやすい仕組みと心理的安全性
ヒヤリハットを報告するには、「誰でも」「気軽に」「安心して」伝えられる環境が必要です。報告がしやすい職場には、次のような要素があります。
- 報告しても責められない風土がある
- 上司や先輩が率先して自らのヒヤリハットを共有している
- 報告内容に対して「ありがとう」の言葉を返す文化がある
- 評価や査定に悪影響を与えないルールが明確になっている
- 形式ばらずに報告できる仕組み(簡単な入力フォームなど)が用意されている
こうした取り組みによって、一人ひとりが安心して行動でき、ヒヤリハットの共有が自然と習慣化されていきます。
情報共有を日常化する方法
ヒヤリハットをチーム全体の学びに変えるには、情報を日常的に共有する仕組みが有効です。たとえば、次のような工夫が挙げられます。
- 週次ミーティングでヒヤリハットの共有時間を設ける
- チャットツールや社内掲示板で報告・共有できる環境を整える
- 報告された内容を「事例集」として蓄積し、新人教育などに活用する
情報共有が日常業務の一部になれば、同じミスを防ぐだけでなく、社員同士の意識向上にもつながります。
ヒヤリハットをきっかけに重大事故を防ぐには
ヒヤリハットを「気づいて終わり」にせず、重大事故の発生防止につなげるためには、業務プロセスや仕組みを見直し、改善を続けていくことが重要です。ここでは、現場で実行しやすく、持続可能な対策方法についてご紹介します。
マニュアル・手順書の整備と見直し
ヒヤリハットを防ぐためには、業務のやり方が誰でも同じように実行できる状態に整えられていることが大切です。そこで有効なのが、マニュアルや手順書の活用です。
業務が属人的になっていると、判断や行動がばらつき、ヒヤリハットのリスクが高まります。業務内容や手順を標準化した状態で、その内容をマニュアルにまとめて共有すれば、誰でも同じ品質で業務を遂行できるようになり、ミスの防止にもつながります。また、過去のヒヤリハット事例をマニュアルに盛り込み共有することは、同様のヒヤリハットを予防する効果があります。
関連記事
「マニュアル校正の基本とは?見落としがちなポイントを徹底解説」
チェックリストやツールの活用
マニュアルとともに活用したいのがチェックリストです。業務の各プロセスで確認すべき項目をリスト化することで、抜けや漏れを防ぐことができます。
チェックリストの効果的な使い方として、以下のような活用方法があります。
- 日常点検やルーチン作業の確認事項を整理する
- 作業前・作業後の確認項目を明文化して習慣化する
- 引継ぎ時の抜け漏れを防止するチェック項目として利用する
- スマホやタブレットを用いてリアルタイムにチェック・記録を行う
- 複数人でのダブルチェックを前提とした共同チェックリストを作成する
これらを活用することで、一人ひとりのリスク意識を高めると同時に、組織全体の業務品質も安定します。
教育・訓練によるリスク感度の向上
どれだけマニュアルやツールを整えても、最終的には人の意識が大切です。ヒヤリハットを未然に防ぐには、リスクに気づける感度を育てる教育や訓練が欠かせません。
定期的な研修やOJTを通じて、「なぜこの手順があるのか」「どんなミスが過去にあったのか」などを伝えることで、理解と納得を持った行動が促されます。特に新入社員や異動者に対しては、ヒヤリハットの事例を活用した教育が効果的です。
継続的な改善活動とPDCAの活用
ヒヤリハットの対策は一度実施して終わりではありません。業務の変化や人の入れ替わりに対応するためには、継続的な見直しと改善が必要です。
その際に役立つのがPDCA(Plan・Do・Check・Act)サイクルの考え方です。それぞれのステップにおいて以下のような意識が求められます。
- Plan(計画):過去のヒヤリハット事例や現場の声をもとに、改善策を計画する
- Do(実行):計画に基づいて具体的な対策を現場で実施する
- Check(評価):対策の効果や現場の変化を確認し、記録する
- Act(改善):効果が薄い場合は手法を見直し、次のサイクルに活かす
このように、ヒヤリハットの情報を活かした継続的な改善活動によって、安全性と業務の質を高めることができます。
株式会社フィンテックスでは、お客様のご予算に応じて「マニュアルのあるべき姿」を、さまざまな視点からご提案しています。
他社には無い、コンサルティングがフィンテックスの強みです。
お客様の現状をヒアリングし、ご希望・ご要望を伺ったうえで業務改善につなげるマニュアルを作成いたします。
詳しいマニュアル制作の実績については、以下をご覧ください。
業務マニュアル 超大型の業務マニュアル編纂プロジェクト。制作チームを編成した初動準備、さまざまなドキュメント制作の提案や柔軟な対応、20,000ページ以上のマニュアル作成、細やかなフォローなど。途中からチームを拡大し、柔軟な対応でご評価いただきました。 業務マニュアル データ形式も見た目もバラバラだったマニュアルを読みやすい構成に作り直し、写真画像の補正、印刷、製本までを一括で対応しました。現場で活用できる「使える」マニュアルになったとご評価いただきました。 ヒヤリハットは、重大事故を未然に防ぐための重要なシグナルです。事故が起きてから対策を講じるのではなく、日々の業務の中で小さな異変や違和感に気づくことが、リスクの芽を摘む第一歩となります。 そのためには、一人ひとりがリスクに対する意識を高め、気づいたことを共有しやすい環境を整えることが欠かせません。報告しやすい雰囲気づくりや情報共有の仕組み、そしてマニュアルやチェックリストといった仕組みの整備が、職場の安全文化につながっていきます。 また、ヒヤリハットへの対応をきっかけとした業務改善を進めていくには、継続的な見直しと教育が必要です。業務マニュアルや手順書をただ作るのではなく、現場の声や変化に合わせて進化させていく姿勢が求められます。 フィンテックスは、マニュアル作成を通じて、ヒヤリハットなど業務課題の解決をサポートしています。マニュアルに関する課題をお持ちの場合は、ぜひ当社にご相談ください。 フィンテックスでは各種業務マニュアルの作成を行っているので、ぜひご相談ください。 監修者 企画営業部 営業本部長 / 経営学修士(MBA) <略歴> フィンテックスにて、マニュアル作成に関する様々な顧客課題解決に従事。
金融系からエンターテインメント系まで様々な経験から幅広い業務知識を得て、「分かりやすいマニュアル」のあるべき姿を提示。500社以上のマニュアル作成に携わる。また、複数の大企業でマニュアル作成プロジェクトの外部マネージャーを兼務している。
趣味は茶道。
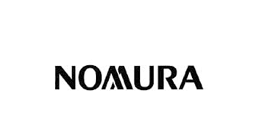

まとめ

月刊エコノミスト・ビジネスクロニクルで取材していただきました。ぜひご覧ください。
https://business-chronicle.com/person/fintecs.php
マニュアルアカデミー
最新コンテンツ

金融業務マニュアル作成のポイントと制作事例を紹介
2025.12.26
マニュアルのご相談・お問い合わせ
マニュアル作成に関するご相談やお悩みがございましたら、お気軽にお問い合わせください。
-
24時間受付中!
翌営業日にご連絡いたします。 -
資料を無料配布中!
マニュアル作成のコツを伝授します。