-
平日9:00-18:00
- mail お問い合わせ
マニュアルアカデミー
- ホーム
- マニュアルアカデミー
- 建設業の業務改善を進める方法は?課題と活用したいツール
建設業の業務改善を進める方法は?課題と活用したいツール

建設業界は慢性的な人手不足が続いており、業務改善の必要性は高いと考えられます。 従来の方法を続けるのではなく、人手不足や長時間労働といった課題の解決につながる業務フローの見直しや、ITツール・AIの導入などの検討が重要です。
しかし、具体的にどのように業務改善を進めていけばよいかわからず困っている方もいるでしょう。 そこで、本記事では建設業で業務改善が求められる理由や多くの現場で抱えている課題、活用したい便利ツールなどを解説します。
この記事を読むことで建設業界の業務改善の進め方がわかるようになるので、ぜひご覧ください。
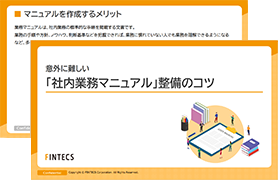
プロが解説!マニュアル作成のコツ
500社以上のマニュアルを支援してきたマニュアル作成のプロが業務マニュアルの作り方を解説しています。
目次
建設業で業務改善が必要とされる背景
建設業で業務改善が求められる課題とは
建設業の業務改善を進める方法
建設業の業務改善で活用できるツール
建設業の業務改善におけるメリット
業務改善の重要性を知り、取り組んでいくことが重要
建設業で業務改善が必要とされる背景
建設業は、早急に業務改善が必要とされる業種といえます。
その大きな理由は、人手不足の深刻化と働き方改革における労働時間の制限の2つによるものです。
建設業において業務改善が必要とされるこれら2つの背景から見ていきましょう。
人手不足の深刻化
国土交通省のデータによると、建設業界では55歳以上が35.5%、29歳以下が12.0%となっており、高齢化が進行しています。
全産業で見ると29歳以下は16.6%ですが、建設業では12.0%と、若い働き手が不足している状況です(※)。
人手不足が慢性化すれば1人当たりの作業負担が大きくなってしまうこともあるでしょう。しかし、業務改善を実施することで効率的な作業につなげ、負担を減らすことが可能です。
建設業は辛く大変な仕事といった認識がよい方向に変わっていけば、若年層の獲得につながる可能性があります。
(※)
参考:(PDF)国土交通省:最近の建設業を巡る状況について[PDF]
働き方改革における労働時間の制限
以前は、各自の判断で早朝や深夜まで業務を行い、なんとか納期に対応していたケースもあったでしょう。
しかし、政府では働き方改革を推進しており、労働時間の上限規制が導入されました。これには建設業も含まれており、時間外労働を無制限に行うことが難しくなっています。
基本的に、月45時間・年360時間の上限を超えて従業員を働かせることはできなくなりました。通称「2024年問題」です。
業務時間を増やすことで対応できていたケースでも、労働時間の制限によってそれが難しくなり、現状のままでは納期の遅延やコストの増加を避けられません。
これも建設業において業務改善が必要な大きな理由のひとつです。
建設業で業務改善が求められる課題とは
建設業が抱える課題の中でも特に大きいのは、人手不足と長時間労働の問題です。
しかし、それ以外にも下請けへのしわ寄せ、古い慣習といった課題も絡み合っています。これらは相互に関連しているため、建設業で業務改善を進めるには、それぞれの課題に対する対策が必要です。
ここでは、建設業で業務改善が求められる大きな課題を4つ解説します。
人手不足
紹介したように建設業界では人手不足の状態となっており、特に若い世代において人材不足が深刻化しています。さらに2024年問題もあり、限られた人が無理をして長時間働くことでなんとかなる状況でもなくなりました。
人手不足の中、無理に納期に対応しようとすると、焦りや疲労から効率が下がったり、集中力の低下によるミスが発生したりすることもあるでしょう。
労働環境が過酷になれば離職率も高まり、さらに状況が悪化していくことも考えられます。
業務改善を行わずに事業を継続するのは難しいといえます。
長時間労働
建設業ではさまざまな立場の業者が建築に関わるため、各工程で工期の厳守が求められます。
しかし、人員が不足している問題もあるため、対応するためには残業や休日出勤を検討しなければなりません。
その結果、大きな問題となるのが長時間労働です。休みなく働く環境が続けば、肉体的な疲労だけでなく精神的なストレスも抱えることになります。
一般的に建設業では複数の建設会社が協力しながら工事を進めていることもあり、自社だけで長時間労働の是正に取り組むのは難しいことも課題です。
下請けへのしわ寄せ
建設業で大きな課題となっているのが、重層下請構造です。
1次下請け、2次下請けだけではなく、さらにその下に下請け企業が存在しています。工事の分業化が進む一方で、途中でマージンが発生するため下位下請けが受けとれる利益が少なくなったり、指揮系統が複雑化して納期調整や施工管理が難しくなったりすることなどが問題です。
特に元請けがコストの削減や納期の短縮を考えた場合、そのしわ寄せが下請け業者への負担を増やしてしまうことがあります。
過度なしわ寄せへの対応は、品質の低下や安全管理の甘さに直結します。
下請けのしわ寄せをできるだけ小さくするためには、業務効率化が必要です。
古い慣習
建設業界では、古くから行っている慣習も多く、それがムダな作業につながっていることがあります。
たとえば、かつては必要だった作業に、今ではほとんど意味がなくなっているにも関わらず時間を費やしているケースです。
さらに、建設業で昔から当然のように行われてきたものに、紙の図面やFAXでの連絡といった、アナログな方法を用いた業務慣習があります。
近年は多くの企業でデジタル化が進んでいますが「昔からこのように進めてきたから」といった固定観念が、新しい便利な技術やシステムの導入を妨げてしまうことも珍しくありません。
業務改善のためには、時代遅れとなってしまった古い慣習は柔軟に見直していくことも重要です。
建設業の業務改善を進める方法
実際に業務改善を進める前に考えておきたいのは、複数の方法を組み合わせて取り組むことです。
業務フローと人事制度の見直し、便利なITツールやAIの導入、業務委託や外注について検討してみましょう。
それぞれ押さえておきたいポイントを解説します。
業務フローの見直し
現在、現場や事務処理に関する業務フローに問題がある場合は、それらを見直すことから始めましょう。
そもそも、業務改善をしようにも、どこに問題や課題があるのかわからないケースもあるはずです。
このような場合には業務フローを見直すことで問題となっている部分を把握しやすくなります。慣習として行っていた業務の中には、現在では不要だったり、他の方法に変更することで効率化が目指せるものもあるでしょう。
業務フローを見直す際に「この業務は本当に必要か」「他の方法とまとめられないか」と考えることで作業の効率化につながります。
人事制度の見直し
人材の確保や定着に関して問題があると感じる場合は、人事制度の見直しが必要です。
建設業全体を通して若い人材が不足している傾向が顕著に見られるため、若い人材が定着しやすい環境を整えておきましょう。
「建設業=過酷」のイメージもあるため、テレワークの推進や、労働者が自由に始業時間や終業時間を決められるフレックスタイム制を導入するのも効果的な方法です。
また、従業員のモチベーション向上のために、技術力の向上を評価に反映させる仕組みを導入するのもよいでしょう。若い人が魅力を感じるような人事評価制度の導入が有効です。
公平で透明性の高い評価基準を示すことは、離職防止や企業への信頼向上に効果を発揮します。
さらに、キャリア形成を支援する研修制度や資格取得補助を整備することで、長期的な定着につながります。
ITツールやAIの導入
業務効率化のために積極的に導入を検討したいのが、日々の業務をサポートするITツールやAIです。
建設業では紙ベースで契約書や図面、写真などの保管・管理を行っている部分もあるでしょう。
これらをデジタル化していくことにより、業務改善が期待できます。
また、AIを活用することで危険予知に役立つ場合や、高精度の画像認識機能によって業務効率化に貢献する場合もあります。
注意点として、ITツールやAIは、導入すれば必ず業務改善につながるとは限りません。
自社のニーズに全く合っていないものを選択すると、コストだけがかかってしまうことも考えられます。導入するツールに関しては慎重に選択しましょう。
さらに、導入後は従業員に対する教育や運用ルールの整備も欠かせません。
実際に現場で使いこなせるようになるまでサポート体制を整えることで、大きな効果につながります。
関連記事
「総務は業務改善により各種効率化が可能!役立つツールも解説」
業務委託や外注
人手不足の問題があり自社で対応するのが難しい部分については、業務委託や外注も選択肢のひとつです。
特に専門性が高い分野については自社で無理に行わず、外部のリソースも活用しましょう。
そのためには、自社で行わなければならないコア業務と、他社に任せられるノンコア業務を見極めることも重要です。
業務委託や外注には費用がかかりますが、現場のワークライフバランス向上や従業員の負担軽減にも役立ちます。
無理をして働いていた従業員も心と体力に余裕が持てるようになれば、業務の効率化につながっていくはずです。
建設業の業務改善で活用できるツール
業務改善を効果的に進めたい場合は、ツールの導入を検討してみましょう。
人の手で行うと時間がかかってしまう作業であっても、ツールを活用することで短時間で対応できるようになります。
特に注目したいのが、現場管理アプリ、ドローン、ウェアラブルカメラの3つです。それぞれ解説します。
現場管理アプリ
現場管理アプリとは、工程の管理や作業進捗の把握、図面の共有などを総合的に行えるアプリです。
これまで別々の手段で行っていたことをひとつの現場管理アプリでできるようになるため、建設業の業務改善に大きく貢献します。
これは、ペーパーレス化にもつながるポイントです。
また、口頭での伝達ミスが起こることもありますが、現場管理アプリを使って連絡をとることで、そうしたミスも減らせるでしょう。アプリ上で業務の一元管理が可能となります。
ただし、現場管理アプリといっても、具体的に何ができるかは使用するアプリによって異なります。
自社で必要とする機能が搭載されているか事前に確認しておきましょう。
ドローン
測量や現場の空撮などを行う際に活躍するのが、ドローンです。これまで手作業で行っていた測量作業をドローンで行うことで、作業を効率化できるだけではなく、精度を高められます。
測量では距離・角度・高さを測定する必要がありますが、従来の測量機器による作業は大きな手間がかかります。
特に測量範囲が広いケースや高低差が大きいケースでは重労働となってしまいます。
人件費もかかりますが、上空から撮影できるドローンを活用すれば、短期間で作業を完了することが可能です。
また、高所での検査などをドローンで行えば、人が高所に上る必要がなくなるため、安全性を高められる点も特徴となります。
撮影したデータを3Dモデルの作成に活用することもできます。
ウェアラブルカメラ
ウェアラブルカメラとは、胸ポケットやヘルメットなどに装着することで、手を使わずに撮影が可能な小型カメラのことをいいます。
ウェアラブルカメラを導入することにより、各種確認をリモートで行うことが可能です。
定点カメラと比較すると細部まで確認できることから、より正確な作業の進捗状況や問題点を把握するのに役立ちます。
カメラを手に持たずに撮影できるため、安全性を確保しながら作業できる点も大きなメリットです。
建設業の業務改善におけるメリット
建設業で業務改善を実施することにより得られるメリットは多々あります。
特に大きいのが、生産性の向上、ムダ時間の削減、スムーズな情報共有の3つです。それぞれポイントを押さえておきましょう。
メリット①生産性の向上
業務改善によって不要な業務が削減されたり、見直されたりすることで、生産性が向上します。
限られた人材で効率的な作業ができるようになれば、人手不足状態に陥っている現場でも対応できることが増えるでしょう。
また、現場作業とオフィス業務でうまく連携できていないことも生産性の低下を招きますが、業務改善で各種システムやツールを活用することで連携も取りやすくなります。
メリット②ムダ時間の削減
業務改善を進める中で、不要な業務をまとめたり見直したりして削減していくことになります。
これは、ムダ時間の削減につながるポイントです。
残業時間や待機時間、移動時間が削減されれば、人件費を抑えることも可能になります。ムダ時間を削減すれば行うべき業務が凝縮されるので、従業員側もワークライフバランスを保ちやすくなる点も大きなメリットといえるでしょう。
離職率の低下につながることも期待できます。
メリット③スムーズな情報共有
スムーズな情報共有のために活躍するのが、便利なITツールです。業務改善で情報共有に役立つITツールを導入することで、業務担当者同士が情報共有しやすくなります。
これらをすべて紙で行おうとすると印刷や受け渡しの手間が発生しますが、そういったものもなくなるほか、印刷コストの削減も可能です。
業務改善の重要性を知り、取り組んでいくことが重要
いかがだったでしょうか。建設業で業務改善が求められる理由や、進め方のポイントなどについて解説しました。
活用できる便利なツールについてもご理解いただけたでしょう。
建設業界では人手不足や長時間労働といった多くの課題が深刻化している状況です。改善のためにも自社に適した方法を検討し、実践していきましょう。
取り組みのひとつとして、各種マニュアルを作成するのも効果的です。たとえば、新入社員が業務をまず理解して現場業務に入りやすくするためのものや作業手順書などが挙げられます。
マニュアルはわかりやすく作成することが重要です。
マニュアル作成にお困りの際は、専門家であるフィンテックスまでご相談ください。
既存マニュアルの見直しなどにも柔軟に対応しています。
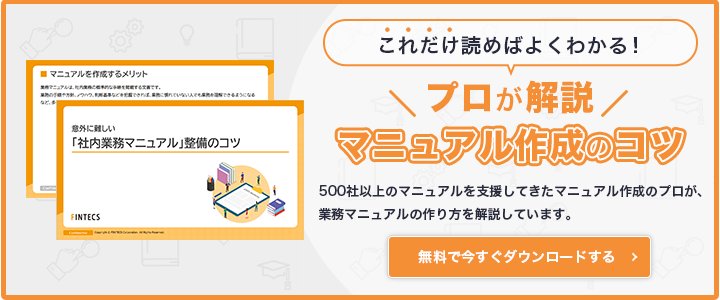
監修者 企画営業部 営業本部長 / 経営学修士(MBA) <略歴> フィンテックスにて、マニュアル作成に関する様々な顧客課題解決に従事。
金融系からエンターテインメント系まで様々な経験から幅広い業務知識を得て、「分かりやすいマニュアル」のあるべき姿を提示。500社以上のマニュアル作成に携わる。また、複数の大企業でマニュアル作成プロジェクトの外部マネージャーを兼務している。
趣味は茶道。
月刊エコノミスト・ビジネスクロニクルで取材していただきました。ぜひご覧ください。
https://business-chronicle.com/person/fintecs.php
マニュアルアカデミー
最新コンテンツ

金融業務マニュアル作成のポイントと制作事例を紹介
2025.12.26
マニュアルのご相談・お問い合わせ
マニュアル作成に関するご相談やお悩みがございましたら、お気軽にお問い合わせください。
-
24時間受付中!
翌営業日にご連絡いたします。 -
資料を無料配布中!
マニュアル作成のコツを伝授します。








