-
平日9:00-18:00
- mail お問い合わせ
マニュアルアカデミー
- ホーム
- マニュアルアカデミー
- ビジネスマナー教育の内容とは?効果を高めるポイントも確認
ビジネスマナー教育の内容とは?効果を高めるポイントも確認

社会人として企業の一員となり働くために欠かせないのがビジネスマナーです。
たとえ優れたスキルを有していても、基本的なマナーが身についていないと周囲に迷惑をかけ、業務に支障を生じさせることがあります。
しかし、ビジネスマナー教育を実践する立場の人事担当者や研修担当者の中には、どのように進めればよいのかわからず、悩んでいる方もいるでしょう。
そこで、ビジネスマナー教育に含めるべき内容やポイントを解説します。
この記事を読むことで具体的な進め方や注意しておきたいことがわかるようになるので、ぜひご覧ください。
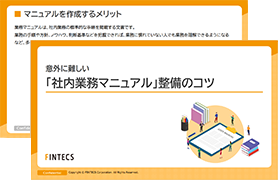
プロが解説!マニュアル作成のコツ
500社以上のマニュアルを支援してきたマニュアル作成のプロが業務マニュアルの作り方を解説しています。
目次
ビジネスマナー教育とは
ビジネスマナー教育が必要な理由
ビジネスマナー教育にあたって整えるべきこと
ビジネスマナー教育で教える内容
ビジネスマナー教育の主な形式
ビジネスマナー教育の効果を高めるポイント
自社に適した方法を選択することが重要
ビジネスマナー教育とは
そもそもビジネスマナー教育とは、社会人に必要な基本的な礼儀や行動規範を学ぶために行われる教育や指導です。
ビジネスマナー教育では、身だしなみや挨拶、報連相、時間を厳守することといった基本行動から、ビジネスにおいて必要となるスキルまで幅広く身につけることになります。
教育を実施する際には一方的な指導にとどめず、受講者が納得し行動に移せる内容を伝えることが重要です。
実際に指導する側が「ビジネスマナーを身につけるのは当然のこと」と考えていたとしても、指導される側が同様に思っているとは限りません。
このような状況で教育を行っても効率が悪くなるため、注意が必要です。
ビジネスマナー教育が必要な理由
受講者に自分ごととして認識してもらうには、なぜビジネスマナーが大切なのかを事前に伝えることが有効です。
そのためには、教育を行う側がビジネスマナー教育を実施する理由や、期待できる効果を正しく理解しておきましょう。
ここでは、ビジネスマナー教育が必要な3つの理由について解説します。
理由①相手に不快感を与えないため
ビジネスにおいて、最低限のルールとも言えるのが相手に不快感を与えないことです。
たとえば挨拶の仕方に問題があったり、言葉遣いが乱暴だったりする場合は、相手に強い不快感を与えてしまう恐れがあります。
どれほど仕事ができる優秀な人であっても、悪い印象を与えてしまうことは避けられません。
本人に悪気がなくても悪い印象を与えてしまった場合は、非常にもったいないことです。
場合によっては商談がうまくいかないなどのトラブルにつながる恐れも十分に考えられます。
ビジネスマナー教育を受けることにより、取引先や上司に対する正しい接し方や振る舞いを学ぶことができます。
理由②ビジネスパートナーとしての信頼を得るため
ビジネスマナーを身につけることは、他社からの信頼を獲得するためにも欠かせません。
特に新入社員や若手社員など業務に不慣れな社員の場合、無意識のうちに失礼な言動をとってしまい、取引先からの信頼を得るのが難しくなることがあります。
事前にビジネスマナーを身につけておけばそのようなリスクを減らし、本人や会社の評価が下がるのを防ぎやすくなるはずです。
これは、ビジネスパートナーとして信頼を得る上でも重要なポイントです。
個人や企業としての信頼性は、成果や売り上げに直結するため、非常に重要な要素と言えるでしょう。
理由③企業イメージの向上につながるため
社員をしっかり教育し、基本的なビジネスマナーを身につけさせておくことは企業イメージの向上につながります。
社会人である以上、ビジネスマナーは身についていて当然のものです。
企業は新人社員や若手社員を育てなければならず、基本的なビジネスマナーを身につけさせるために取り組まなければなりません。
これを怠った場合は企業自体に問題があると判断される可能性もあります。
反対に、社員全員がきちんとしたビジネスマナーを身につけておくことで「誠実な会社」と思ってもらえるようになるでしょう。
ビジネスマナー教育にあたって整えるべきこと
ビジネスマナー教育を実施する際は、どのようなことを事前に整えておけばよいのでしょうか。
いきなり研修を始めるのではなく、事前にしっかりと準備しておくことが大切です。
大切なのは、教育方針や目的を明確にすること、現状の課題を把握すること、そして社内で共通意識を形成することの3点です。以下で順に解説します。
教育方針や目的を明確にする
はじめに行いたいのは、何のためにビジネスマナー教育を実施するのか、目的を明確にしておくことです。
確かにビジネスマナーは身についていて当たり前とも言えるものではありますが、目的が不明瞭なままで始めても受講者にとって心に響く教育はできません。
結果として成果に結びつかず、時間が無駄になってしまうこともあるでしょう。
教育方針や目的を明確にしておくことでゴールも設定しやすくなります。
たとえば、以下のような目的が代表的です。
【教育方針・目的の例】
- 新入社員として理解しておくべき社会人としての心構えや姿勢を理解する
- 社内外での円滑なコミュニケーションにつなげる
- 顧客に安心感を与えられるような対応力を身につける
企業が新人社員や若手社員をどのように育てたいのか、どのように活躍してほしいのかを考えると、イメージしやすくなります。
現状の課題を把握する
ビジネスマナー教育を効果的な形で実施していくためには、現状の課題を正しく把握することが欠かせません。
どのような課題が発生しているのかを明確にしておくことで、その課題に沿った具体的な研修内容を計画しやすくなります。
たとえば、ビジネスシーンに適した電話応対やメール作成に課題がある場合は、それらを改善するためのビジネスマナー教育を検討します。
課題を把握するためには、顧客アンケートやクレーム内容の確認、現場リーダーやマネージャーへのヒアリングなどを実施するとよいでしょう。
現場の声を反映することにより、実務に直結する形でビジネスマナー研修の内容を検討しやすくなります。
ビジネスマナー教育を受ける社員にもアンケートをとり、受講者が実感している課題を確認する方法も効果的です。
社内での共通意識を形成する
ビジネスマナー教育でよくある失敗の一つが、社内での共通意識を形成できていない問題です。
たとえば、ビジネスマナー教育で学んだ内容と、先輩社員や上司の対応や指導の内容が異なる場合、受講者は戸惑ってしまうことでしょう。
このようなトラブルを避けるためには、先輩や上司層にもマナー研修を実施し、どのように指導すればよいかを理解してもらうことが大切です。
担当者によって教育内容が異なると混乱が生まれやすくなるため、マニュアルを整備して教育担当者が参照できる状態にしておくのもよいでしょう。
上司や先輩が指導する際、教育マニュアルを参照することで個人差のない共通の指導を行いやすくなります。
ビジネスマナー教育で教える内容
ビジネスマナー教育を実施する際には、具体的に何を教えるか、その内容について考えておきましょう。
基本中の基本とも言える以下の8点については、すべて入れておくことをおすすめします。
マナー①身だしなみ
身だしなみは、その人がどのような人物なのかを判断するためにも重要なポイントであり、身だしなみによって相手に与える印象も変わります。
特に身だしなみに問題があるために第一印象が悪くなってしまうと、安心感や信頼感を取り戻すまでに時間がかかることもあります。
そのため、ビジネスマナー教育でビジネス向けの基本の身だしなみについてしっかりと学んでもらうことが大切です。
ビジネスマナー教育では、スーツのしわや靴の汚れなど、細かいところにまで目を向けられるように指導します。
マナー②挨拶
ビジネスにおいて基本中の基本とも言えるのが、挨拶です。
明るくはっきりとした挨拶ができるだけでも相手に好印象を与えやすくなります。
一方、挨拶がきちんとできないとどれだけ仕事ができても相手を不快にさせたり、不安に感じさせたりすることもあるでしょう。
ビジネスマナー教育では単純に「おはようございます」といった基本の挨拶だけではなく、表情の作り方やTPOに合わせた挨拶の使い分けなどを学びます。
マナー③時間の厳守
約束の時間を守れない人は、会社や取引先に大きな迷惑をかけてしまうことがあります。
そのため、時間厳守について正しい知識を持つことが重要です。
時間を守ることの重要性を理解するのはもちろんのこと、どのようにすれば約束していた時間に遅れずに済むか、効率的な時間管理の方法なども含めて教育しましょう。
特に、まだ学生気分でいる新人社員の場合は時間厳守の意識が身についていないこともあるため、しっかりと理解してもらう必要があります。
マナー④報連相
業務を円滑に進めるために不可欠なマナーが、報連相(報告・連絡・相談)です。
業務上起こり得るトラブルの中には、報連相が適切にできていなかったために発生してしまうものも数多くあります。
ビジネスマナー研修では、報連相の重要性に加えて、具体的な実践方法も身につけられる内容にする必要があります。
また、報連相が適切に行えなかった場合に発生するリスクについても理解してもらいましょう。
マナー⑤言葉遣い
言葉遣いは本人の印象を大きく左右するポイントであり、同時に企業の評価とも関わってきます。
挨拶などと同様にビジネスマナーの基本とも言えるものです。
しかし、これまで使ってきた言葉遣いを変えるのは簡単なことではありません。
特に、多くの新人社員がつまずきやすいのが、尊敬語・謙譲語・丁寧語の区別です。
難しい部分もありますが、正しい言葉を選ばなければ、場合によっては取引先などに失礼な対応になり、気分を害してしまったりする恐れもあります。
丁寧な言葉を選んだつもりが、上司に対して「了解しました」と答えるなど、目上の人には適さない表現を選んでしまうこともあるでしょう。
ビジネスマナー教育でしっかりと基本を身につけさせることが重要です。
マナー⑥電話対応の方法
電話対応は直接顔を合わせて話をするわけではないため、声や言葉遣いで相手に誤解なく意思疎通ができるようにしなければなりません。
取り次ぎによるミスを避けるためには、内容をメモしたり、正確に電話の内容を復唱したりする確認方法などを身につけることも重要です。
一方的に指導するだけでは身につかないため、ロールプレイング形式での学習が適しています。
電話に苦手意識を持つ人も多いため、自信を持って対応できるように教育体制を整えておきましょう。
マナー⑦メールの書き方
現代は対面以外でビジネス関連のやりとりをすることも増えており、メール対応についても正しく学んでおかなければなりません。
チャットについても同様です。
わかりやすい件名をつけることや、宛名や結びの適切な使い分け、文章の内容など、ビジネスで注意すべき点は多くあります。
誤送信やCC/BCCのミスが大きなトラブルにつながることもあるため、教育の中で重点的に扱う必要があります。
マナー⑧名刺交換の方法
学生の頃には経験がなく、戸惑ってしまうことが多いのが名刺交換です。
取引先と名刺交換をする際、不適切な方法で行うと「会社の教育が行き届いていない」と思われる可能性があります。
自己紹介の仕方や正しい名刺交換の方法、名刺の管理方法など、学ぶべきことは多くあります。
また、近年はオンライン名刺交換も普及してきました。
デジタルツールを活用した名刺交換に関して学んでおくことも重要です。
実際に経験しなければ身につかない部分もあるため、ロールプレイングでのトレーニングが向いています。
関連記事
「総務は業務改善により各種効率化が可能!役立つツールも解説」
ビジネスマナー教育の主な形式
ビジネスマナー教育には、さまざまな形式があります。
それぞれの特徴を知り、自社に適したものを導入しましょう。
ここでは、代表的な形式について解説します。
集合型研修
集合型研修は、受講者が会場に集まり、講師から直接指導を受ける形式です。
会議室やセミナールームなどで実施されます。
直接参加するスタイルであり、講師からすぐにフィードバックを受けられるため集中力を保ちやすい一方、会場手配のコストや日程調整の難しさなどがデメリットです。
OFF-JT
OFF-JTは、社外セミナーや研修施設など、職場以外の場所で行われる教育訓練です。
学習に集中しやすく効率的にノウハウを得られるのがメリットです。
しかし、受講料や会場費用がかかること、従業員が社外で学ぶことから職場は一時的に人手不足になりやすいことなどに注意しなければなりません。
オンライン研修
オンライン研修は、Zoomなどのオンライン会議ツールを用いて、リアルタイムに講師と受講者がつながる形式です。
会場費が不要でコスト削減につながりますが、通信環境が必要なことや、集中力が切れやすいことなどがデメリットです。
eラーニング
eラーニングは、インターネットを利用した学習システムです。
自分のペースで動画や教材を活用して学べることから無理なく実施しやすいことや、反復学習に向いているメリットがあります。
しかし、自主的に学ぶ意思がなければ効果が薄くなる点に注意が必要です。
グループワーク
グループワークは、少人数のグループに分かれ、課題を解決する形で行う学習です。
他の参加者の意見を聞くことで視野が広がったり、コミュニケーション能力が身についたりします。
一方で、受講者の積極性によって学べる内容や身につき方に差が出る点はデメリットと言えるでしょう。
ロールプレイング
ロールプレイングは、名刺交換や電話対応のように実際のビジネスシーンを想定し、各役割を演じて学習する方法です。
即戦力につながる知識が身につきます。
ただし、人によっては恥ずかしさから積極的に参加できないこともあります。
ビジネスマナー教育の効果を高めるポイント
ビジネスマナー教育の効果を高めるために重要なポイントを6つ解説します。
ポイント①習得する目的を明確に伝える
実際にビジネスマナー教育を始める前に、受講者に対してビジネスマナーを習得する目的を明確に伝えておきましょう。
目的が曖昧なままだと学習意欲が湧きません。
大切なのは、受講者に「ビジネスマナー教育を受けることで自分にメリットがある」と感じてもらうことです。
ビジネスマナーを習得する目的やメリットを実感できれば、モチベーションの向上や積極的な参加につながります。
ポイント②繰り返し実践する
ビジネスマナー教育といっても、ただ1回実施するだけで完璧に身につくわけではありません。
日々の業務の中で繰り返し実践することで、少しずつ身についていきます。
繰り返し学びやすい環境を整えておくことも、習得効果を高める上で欠かせません。
定期的に練習できる機会を設けることが重要です。
業務の中で実践していく場合は、うまくいかなかった時のことを考慮して先輩従業員がフォローできる体制を築いておきましょう。
ポイント③フィードバックの機会を持つ
成長しているポイントや改善が必要なポイントを知るためには、フィードバックの機会を持つことが欠かせません。
何か問題があった場合はただそれを指摘するのではなく、具体的にどのような形で改善すればよいのかアドバイスを添えましょう。
教育を受けている側は、具体的なフィードバックを受けることによって、誤った行動や態度を改善するきっかけにつながります。
特に新人社員のうちは何が正しくて何が間違っているのか自己判断できないこともあるため、重要です。
ポイント④適任の講師を選ぶ
誰を講師に選ぶのかも結果を左右します。
たとえば、自分の体験や考え方を一方的に押し付けるような人を講師に選ぶと、偏った教育になってしまう恐れがあるため、注意が必要です。
仕事ができることと教え方がうまいことは、別の能力です。
教育の内容がわかりにくい、役に立たないと判断されると一気に受講者のモチベーションが下がってしまう可能性もあります。
社内の従業員で適役がいない場合は、外部の専門講師を招くのもよいでしょう。
ポイント⑤自社の風土に合わせて研修内容を選ぶ
ビジネスマナー教育にはさまざまな選択肢がありますが、どのような形で実践していくか悩んでいる場合は、自社の風土を重視するのもおすすめです。
企業によって重視すべきポイントが異なります。
たとえば、企業によって非常に厳格なビジネスマナーを求めるケースもあれば、カジュアルで接しやすいことを重視することもあるでしょう。
自社の風土と全く異なる研修内容を選ぶと、現場でうまく活かせないことがあるため、注意する必要があります。
ポイント⑥eラーニングを導入する
集合研修前後の事前学習&復習などでよく利用されているのが、eラーニングです。
eラーニングではスマホやパソコン、タブレットなどを用いてインターネットを利用し、オンライン環境で学習します。
インターネット環境さえあればいつでもどこでも受講できることから、受講者は自分の都合に合わせて学習できるのが特徴です。
集合型研修などと比較して管理者側の負担も少なく済むため、活用してみましょう。
自社に適した方法を選択することが重要
いかがでしたでしょうか。
ビジネスマナー教育を検討する際に押さえておきたいポイントを解説しました。
代表的な形式や実施すべき内容についてもご理解いただけたかと思います。
さまざまな選択肢がありますが、大切なのは、自社に適した方法を選んで実施することです。
ビジネスマナー研修は、新人社員が入社するたびに継続して実施するものなので、具体的な進め方や注意点をまとめたマニュアルを作成しておくのもよいでしょう。
フィンテックスでは、わかりやすく、現場で本当に役立つマニュアル作成をサポートしています。
これまでに多種多様なマニュアル作成の実績がありますので、ぜひご相談ください。
監修者

企画営業部 営業本部長 / 経営学修士(MBA)
<略歴>
フィンテックスにて、マニュアル作成に関する様々な顧客課題解決に従事。
金融系からエンターテインメント系まで様々な経験から幅広い業務知識を得て、「分かりやすいマニュアル」のあるべき姿を提示。500社以上のマニュアル作成に携わる。また、複数の大企業でマニュアル作成プロジェクトの外部マネージャーを兼務している。
趣味は茶道。
月刊エコノミスト・ビジネスクロニクルで取材していただきました。ぜひご覧ください。
https://business-chronicle.com/person/fintecs.php
マニュアルアカデミー
最新コンテンツ

金融業務マニュアル作成のポイントと制作事例を紹介
2025.12.26
マニュアルのご相談・お問い合わせ
マニュアル作成に関するご相談やお悩みがございましたら、お気軽にお問い合わせください。
-
24時間受付中!
翌営業日にご連絡いたします。 -
資料を無料配布中!
マニュアル作成のコツを伝授します。








