-
平日9:00-18:00
- mail お問い合わせ
マニュアルアカデミー
- ホーム
- マニュアルアカデミー
- 業務改革とは?業務改善との違いと進め方をわかりやすく解説
業務改革とは?業務改善との違いと進め方をわかりやすく解説

企業をよりよい形で成長させていきたいと考えた際、定期的に業務や企業体制の見直しが必要になることがあります。
業務改革は、従来のやり方を根本から見直すことで、会社の成長に寄与する取り組みのひとつとされています。
しかし、そもそも業務改善と何が違うのかわからず、業務改革にどのように取り組めばよいか悩んでいる方もいるでしょう。
本記事では、業務改革の基本から進め方、業務改善との違いまで詳しく解説します。
この記事を読むことによって業務改革について理解が深まり、どのように実践していけばよいかがわかるようになるので、ぜひご覧ください。
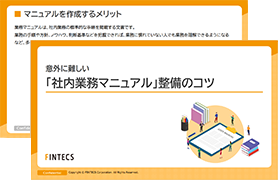
プロが解説!マニュアル作成のコツ
500社以上のマニュアルを支援してきたマニュアル作成のプロが業務マニュアルの作り方を解説しています。
目次
業務改革とは
業務改革と業務改善の違い
業務改革で得られる効果
業務改革の進め方
業務改革を進める手段
業務改革で発生しやすい問題
企業をよりよく成長させていくためにも欠かせない業務改革
業務改革とは
業務改革とは、これまでの組織全体の仕組みや文化、業務フロー、人事評価制度など、さまざまな部分を根本から見直すことで、企業としての競争力や生産力を高めるための取り組みのことをいいます。
BPR(Business Process Reengineering:ビジネスプロセス・リエンジニアリング)とも呼ばれます。
業務改革を行うことで、新たな働き方の導入や新規ビジネスモデルの構築につながる場合もあります。 時代の変化とともに企業を取り巻く環境も変化していくため、他社と差別化を図り、時代に取り残されないためにも業務改革が必要です。
企業が目標を達成するために、どのような改革が必要になるのかを明確にした上で改革を実行していくことになります。
業務改革と業務改善の違い
業務改革と似たものに「業務改善」があります。
どちらも似ていますが、目的や取り組みの規模が異なる点が特徴です。
業務改善では、基本的に現在行っている業務フローを維持する形で、その中から無駄や非効率な部分を減らし、効率化を目指していきます。それほど規模は大きくなく、日常的に行える取り組みが中心です。
一方、業務改革は根本的な部分からの見直しであるため、業務の仕組み自体を大きく変えるような取り組みを行います。
これまで紙ベースで行っていた業務をデジタル化したり、新たな部署を設けて業務を再振り分けしたりするような大規模な取り組みが業務改革です。
現在のやり方を維持したまま改善するのが業務改善であり、やり方そのものを変えるのが業務改革といえます。
業務改革で得られる効果
業務改革を実施することで、さまざまな効果が期待できます。
ここでは、その中でも特に代表的な効果を6つピックアップしました。
業務改革が必要か迷う場合は、以下の効果を確認すれば自社にとってのメリットを判断しやすくなります。
生産性の向上
業務改革によって期待できる効果のひとつが、生産性の向上です。業務改善と比較すると、より大きな生産性の向上が期待できます。
業務改革を行う際には、現在実施している各業務フローや組織構造を可視化した上で再設計することが重要です。
単純に無駄を省くだけではなく、業務の進め方や根本的な役割分担を変更することにより、生産性の向上が可能になります。
業務改善に取り組んでも思うような効果が得られない場合も、業務改革に取り組む段階にあると考えて実施していきましょう。
関連記事
「業務を可視化する目的やメリットは?実施する際の手順をチェック」
コストの削減
業務改革は、各種コストを削減する目的でも役立ちます。
たとえば、アナログでやりとりしていた部分をデジタル化することで印刷コストを削減できるようになるでしょう。
さらに、データ入力や集計などをシステム化することで、作業時間が大幅に削減されて人件費も抑えられます。
事業全体のプロセスや役割配置が適切か見直すことが大切です。
これまで複数部署で行っていた業務を統合する、自社で行っていて時間のかかる業務は外部に委託するなど、仕組みを変更することで人件費やその他コストの削減につながります。
今とは大きく業務フローを変更する形で業務改革を行う場合、導入時には高額な費用がかかることもあるでしょう。
しかし、将来的にはコストの削減につながる可能性があります。
業務の属人化の解消
その担当者しか業務の詳細を把握していない『属人化』が生じていると、その人が休んだり離職したりしたときに業務に対応できなくなってしまいます。
属人化を招く原因のひとつが、組織の役割分担や業務設計の偏りです。 業務改善につなげるためには、根本的に業務フローを見直さなければなりません。 その上で担当範囲を再構築し、標準化やマニュアル化を進めるのがポイントです。
属人化は専門性の高い業務で発生しやすい傾向がありますが、業務をサポートするツールを導入することで、専門的な知識がない方でも対応しやすくなるでしょう。
また、担当者を含め従業員が業務に追われて情報共有が難しい場合、一部の従業員に知識が偏りやすくなります。
こうした問題も、情報共有ツールなどを活用することで業務の属人化を改善できます。
従業員の満足度の向上
業務改革によって業務フローを見直したり、効率化を目指したりすることは、従業員にとって働きやすい環境を整えることにもつながります。
そのため、従業員の満足度向上につながるのも業務改革を実施する上での大きな効果です。
生産性に課題を抱えている現場では、日々の非効率な業務や過度な作業負担により、従業員のモチベーションが低下しているケースもあります。
業務改革により働きやすい環境が整えば、従業員のモチベーションが向上し、離職率を抑えることもできるでしょう。
従業員が仕事にやりがいを感じられる環境を整えることは、企業にとって重要です。
1人1人の従業員がやりがいを感じられるようにするためにも、職場環境の改善に業務改革を取り入れることが有効です。
顧客の満足度の向上
満足度が向上するのは従業員だけではありません。顧客満足度にも直結します。
たとえば、これまで対応に時間がかかっていた業務を業務フローの見直しによってスピーディーに処理できるようになれば、迅速な顧客対応が可能になります。
素早い対応によって、顧客は安心感や信頼感を持つようになるでしょう。
また、作業を効率よく行えるようになれば人件費を節約して生産性を向上でき、それを還元する形で顧客に対して従来よりも安くサービスや商品を提供できる可能性もあります。
従業員が効率的に働けるようになれば、その分、顧客対応に時間をかけられるようになり、よりよいサポートを提供することも可能です。
このように、迅速な対応やコスト削減など複数の要因から、顧客満足度の向上が期待できます。
DX化の推進
DX化を推進するためにも業務改革は役立ちます。
DX(デジタルトランスフォーメーション)とは、デジタル技術を活用して企業全体の競争力や生産性を高める取り組みです。
日本政府も推進しており、特に「レガシーシステム」と呼ばれる古いシステムの見直しが重要とされています。
老朽化して非効率になったり、時代に合わなくなったりしているレガシーシステムを使い続けるのは望ましい状態とはいえません。
場合によっては、システム維持管理費用の高額化につながる場合もあります。
さらに、古いシステムはセキュリティリスクが高まる点にも注意が必要です。
企業のDX化を推進するためにも業務改革を実施していきましょう。
業務改革の進め方
業務改革はどのような手順で進めていけばよいのでしょうか。
全体の流れを把握してから行わないと効率が悪くなってしまうことがあるため、注意が必要です。
ここでは、一般的な流れについて解説します。
目的や目標を明確にする
業務改革に取り組む前に、目的や目標を明確に定めておきましょう。
何のために業務改革が必要なのかを明らかにしておかないと、施策を検討する際に迷走しやすくなってしまいます。
実際に業務改革を進めていくと、途中で意見が分かれたり、修正が必要になったりすることがありますが、目的と目標を掲げておけば、どのように変更すればよいか判断しやすくなります。
目標を設定する際には「年間で残業時間を20%削減する」といった具体的な数値を盛り込むことが望ましいでしょう。
数字を設定しておくことでどの程度達成できているかも把握しやすくなります。
目標を設定する際は、達成可能なものにしておくことも重要です。
毎日のように残業が発生しているのに「1か月以内に残業時間をゼロにする」といった無理な目標の設定は避ける必要があります。
現状の業務フローを可視化する
次に、現状の業務フローを可視化していきます。
現状把握が正しくできていないと、本当の問題や課題を見逃してしまう可能性があるためです。
担当者が1人で行うのではなく、実際に作業を担当している人にヒアリングを行ったり、業務改革を進めるメンバー内で認識の擦り合わせを行ったりする必要もあります。
業務改革では属人化している作業や無駄な手順を見つけることも重要なので、業務フローを可視化していく過程でこちらも確認しましょう。
課題点を洗い出す
現状の業務フローを可視化できたら、それを参考にしながらはじめに設定しておいた目的・目標を達成するために改善が必要な課題やリスクなどを洗い出します。
具体的に課題点を洗い出すことにより、業務改革を行う上でどこに力を入れていけばよいのかを判断できるようになるでしょう。
課題になるのは、コストや生産性だけではありません。
従業員の精神的な面も含めて、課題となりそうな箇所を洗い出していきます。
もし、課題点が浮かんでこないようであれば、その前の段階である「現状の業務フローを可視化する」が十分にできていなかったり、ヒアリングが不足している可能性があります。
必要に応じて現状把握のステップに戻ることも検討が必要です。
新しい業務フローを設計する
洗い出した課題点を解決していくために必要な新しい業務フローを設計します。 改善すべき項目には優先度をつけておきましょう。
優先度の判断が難しい場合は、ECRSという考え方を活用する方法があります。
【ECRS】
- Eliminate(排除):不要な業務をなくす
- Combine(結合):業務をまとめる
- Rearrange(再配置):業務の順番を入れ替える
- Simplify(簡素化):シンプルで時間のかからない方法に変更する
業務フローを参考にしながら、この業務はなくせないか、まとめられないか、といった形でひとつずつ検討していきましょう。
その結果をもとにして新しい業務フローを設計します。
設計したフローを実行する
設計したフローを実際に実行していきます。
ただし、新しく決めたことを突然現場で実施すると混乱につながる可能性があるため、その前に現場で働くメンバーへの周知やトレーニングを行う必要があります。
業務内容が大きく変更されるため、説明会を設けて質疑応答の場も用意しておきましょう。 業務改革によってこれまでとは異なる形で業務を行うことになるため、従業員が不安を感じることもあります。
質問などがあった場合はそれらにしっかりと答えられるように準備が必要です。
また、わからないことがあった際に参照できるマニュアルを整備しておくことで従業員が新しい業務に取り組みやすくなります。
効果を測定する
設計したフローを実行したら、効果測定が重要です。
実行しただけでは、どの程度効果が得られたのか把握できず、成功か失敗かを判断できません。
業務改革によってどの程度改善できたのか、数値や具体的な指標でしっかりと評価しましょう。事前に設定した目標に届かなかった場合は、その原因を見極めることも大切です。
必要に応じてフローを修正し、PDCAサイクルを回してよりよい業務改革を目指しましょう。また、実際に現場で働く従業員から意見を聞くことも重要です。
新しい業務フローでわからない点や困っていることがあれば、それらの課題も含めてフローを修正することで、従業員にとって働きやすい職場づくりにつながります。
業務改革を進める手段
業務改革を進める上で役立つ手段についても確認しておきましょう。
アウトソーシング、システム化、バランススコアカード、シェアードサービスなどの方法があります。
ここでは、それぞれの手段について解説します。
アウトソーシング
自社で行っている業務を外部の専門業者に委託するのが、アウトソーシングと呼ばれる方法です。
たとえば、社内に専門的な業務に対応できる従業員がいない場合、一から育てるよりもアウトソーシングしたほうが人件費を抑えられることがあります。
現在は多くの企業で人手不足の状態にあることから、アウトソーシングの需要が高まっている状況です。
特に、直接的に企業の収益にはつながらないものの、コア業務をサポートする「ノンコア業務」はアウトソーシングに向いています。
一部外部に委託することで従業員の負担を抑えることも可能です。
システム化
これまで手作業で行っていた業務をデジタルツールや専用システムを用いて自動で行うのが、システム化です。
自動で行える部分はツールに任せたほうが素早く、かつミスなく行えます。
システム化を行う際は、あらかじめ組織内で行っている業務プロセスを業務フロー図で視覚化しましょう。
すると、どの部分にシステムを導入することで効率化が目指せそうか見えてきます。
導入時はコストが発生しますが、中長期的に見れば生産性向上につながりやすい手段のひとつとなります。
バランススコアカード
バランススコアカードとは、財務・顧客・業務プロセス・学習と成長という4つの視点から企業の戦略を分類し、経営戦略の分析や評価を行うためのフレームワークです。
BSC(Balanced Scorecard)とも呼ばれます。
それぞれの視点から多角的な評価を行うことで、売上や利益だけに偏らない形で成長に必要な視点を取り入れることが可能です。
シェアードサービス
シェアードサービスとは、グループ会社が行っている管理業務を1箇所に集約し、1つの専門部門で行う仕組みです。
たとえば、経理や人事、労務などのバックオフィス業務を1箇所のシェアードサービスセンターに集約させるような形です。
各法人が個別にバックオフィス人材を雇用する場合と比べ、効率が上がりコストも削減できます。ただし、人材の配置転換や社内システムの整備などが求められることから、初期投資が高額になりやすく、運用開始までに時間がかかる点には注意が必要です。
業務改革で発生しやすい問題
実際に業務改革に取り組んでいく前に、どのような問題が発生しやすいのか理解しておくことをおすすめします。
問題を把握しておくことで、発生しやすい問題を予防したり、いち早く対策を講じたりすることにもつながります。
特に注意したいのが以下の5つです。
プロジェクトが迷走してしまう
業務改革を行う目的や目標を明確に定めずに始めてしまうと、プロジェクトが迷走してしまうことがあります。
具体的に何を実施すればよいのかわからなくなったり、見切り発車で行った改革の調整や修正に時間がかかることもあるでしょう。
このような状況になれば業務改革はなかなかうまくいきません。
成果が得られないまま作業負担が増えると、プロジェクトメンバーから不満が出ることも考えられます。
プロジェクトが迷走してしまうのを防ぐためには、業務改革を行う目標を数値化するのがポイントです。
より明確に目指す部分がわかりやすくなるので、何をすべきかも見えてきます。
現状の業務フローとの変化が見られない
業務フローを新しくしたつもりが、現状とそれほど大きな変化が見られないケースもあります。これは、簡単な業務改善と同様に業務フローの一部を変更しただけの形で業務改革に取り組んでしまったケースです。
特にこれまで長年にわたって行ってきた業務フローの場合、それを大きく変化させることに不安を感じることもあるでしょう。
その結果、無意識のうちに大きな変革を避け、表面的な手順を修正するだけの小規模な変更にとどまる場合があります。
大切なのは業務フローを変更すること自体ではなく、現状の課題を解決できる業務フローにすることです。
あらかじめ課題を十分に洗い出した上でその課題解決につながるような業務フローを検討しましょう。
業務改革の効果を実感できない
業務改革を実施しても、その効果が実感できないことがあります。
効果が実感できなければ、費用や時間がかかってしまったことに対し不満を感じることもあるでしょう。
「ただやらなければならないことが増えただけ」と従業員が思ってしまえば、モチベーションも低下します。
業務改革の効果を実感できない理由はいくつかありますが、正しく効果を測定できていないために実際には効果が出ているもののそれに気づけていないケースも少なくありません。モニタリングをしっかり実施しましょう。
また、数値データで変化を確認することでどのような効果が得られたのか判断しやすくなります。
業務フローの変化に対して現場から反発を受ける
さまざまなことを考慮した結果、業務フローを大きく変化させることで業務改善につながると判断したとします。
しかし、これまでとやり方が変わることに対して現場から反発を受け、実施できないケースもあります。
現場の協力が得られなければ、業務改革を進められません。
反発を受ける理由として多いのが「何のために業務フローを変えるのかわからない」「期待できる効果を理解していない」といった2つです。
これらの理由を理解できていない段階で指示だけされても、前向きに従うのは難しいといえるでしょう。
業務の効率化につながる変化であれば従業員も受け入れてくれる可能性が高くなるので、しっかりとコミュニケーションをとって説明を行うことが重要です。
新しい業務フローに現場が対応しきれない
従業員からの理解が得られて業務フローを変化させたものの、現場が対応しきれずに混乱してしまうことがあります。
特にこれまでと業務フローが大きく変化する場合は前のやり方と勘違いしてしまってミスにつながったり、新たな手順を覚えられず苦戦したりすることもあるでしょう。
業務フローを変化させる以上、ある程度の混乱は避けられない場合もありますが、一度に大きな変更を行うのではなく、スモールスタートで実施することで混乱を抑えられます。
また、新たなシステムや機器を導入した場合はそれらの使用方法に関する研修を実施するなどして、従業員が不安なく業務フローの変更に対応できるようにする取り組みも重要です。
企業をよりよく成長させていくためにも欠かせない業務改革
いかがだったでしょうか。業務改革の概要や実施したいこと、発生しやすい問題などについて解説しました。
業務改善との違いについてもご理解いただけたでしょう。
業務改善よりも大規模な取り組みとなるため、従業員の理解を得て協力しながら継続する必要があります。
業務フローの変更は現場に混乱を招くこともあるので、混乱を抑えるために、作業マニュアルも活用しましょう。
フィンテックスでは、マニュアル作成に関して総合的なサポートが可能です。
ユーザーにとって本当に必要な、役に立つマニュアル作成を行っているため、業務改革に向けたマニュアル整備を検討している方はぜひご相談ください。
監修者 企画営業部 営業本部長 / 経営学修士(MBA) <略歴> フィンテックスにて、マニュアル作成に関する様々な顧客課題解決に従事。
金融系からエンターテインメント系まで様々な経験から幅広い業務知識を得て、「分かりやすいマニュアル」のあるべき姿を提示。500社以上のマニュアル作成に携わる。また、複数の大企業でマニュアル作成プロジェクトの外部マネージャーを兼務している。
趣味は茶道。
月刊エコノミスト・ビジネスクロニクルで取材していただきました。ぜひご覧ください。
https://business-chronicle.com/person/fintecs.php
マニュアルアカデミー
最新コンテンツ

金融業務マニュアル作成のポイントと制作事例を紹介
2025.12.26
マニュアルのご相談・お問い合わせ
マニュアル作成に関するご相談やお悩みがございましたら、お気軽にお問い合わせください。
-
24時間受付中!
翌営業日にご連絡いたします。 -
資料を無料配布中!
マニュアル作成のコツを伝授します。








