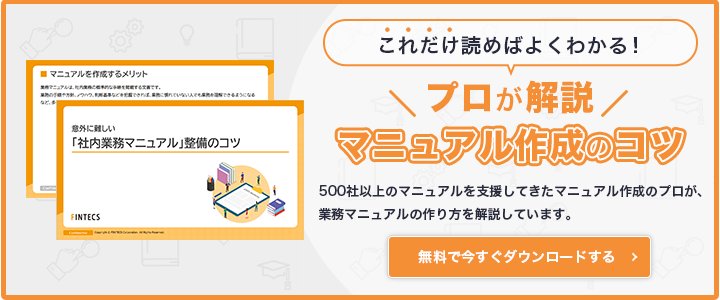-
平日9:00-18:00
- mail お問い合わせ
マニュアルアカデミー
- ホーム
- マニュアルアカデミー
- 業務の効率化につながるルーティンとは?ビジネス上で大切な理由と実践のコツを解説
業務の効率化につながるルーティンとは?ビジネス上で大切な理由と実践のコツを解説

日々の仕事の中で、こんな悩みを感じることはありませんか?
- やることが多すぎて優先順位がつけにくい
- 同じミスを何度も繰り返してしまう
- 毎日忙しいのに成果につながっていない気がする
こうした課題の背景には、「業務の進め方が整理されていない」ことが関係している場合があります。その改善の糸口として注目したいのが、業務の流れを習慣として整える「ルーティン」という考え方です。
本記事では、ルーティンの基本的な意味やビジネスで果たす役割、実践のためのポイントまでをわかりやすく解説します。
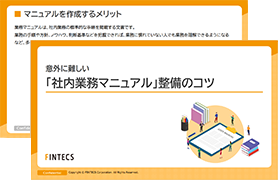
プロが解説!マニュアル作成のコツ
500社以上のマニュアルを支援してきたマニュアル作成のプロが業務マニュアルの作り方を解説しています。
目次
ルーティンとは?ビジネスにおける基本の考え方
ルーティンが業務効率化にもたらす効果
ルーティンを定着させる実践のコツ
まとめ
ルーティンとは?ビジネスにおける基本の考え方
日々の業務を効率よく、安定的に進めるためには「ルーティン」の理解と活用が欠かせません。この章では、ルーティンの基本的な意味やマニュアルとの違い、ビジネス現場で果たす役割について解説します。
ルーティンの一般的な定義
ルーティンとは、同じ動作を繰り返すこと、あるいは特定の行動の前に決まった動作を行うことを指します。
たとえば、「オフィスについたらメールとタスクをチェックする」「請求書が届いたら形式に沿って処理する」など、日常的に同じ動作を繰り返すことがルーティンにあたります。ルーティンが習慣として定着することで、作業の効率化に役立ちます。
また、「始業前にストレッチをする」「プレゼンの前にコーヒーを飲む」など、特定の行動の前にする動作を決めておくことも、ルーティンの一種です。これらの動作は、気分の切り替えや緊張の緩和に有効です。
ビジネスにおけるルーティンの役割
ビジネスの現場では、毎日のルーティンが作業の土台となります。営業日報の作成、定例ミーティングの実施、顧客対応後の記録入力など、繰り返される業務は数多くあります。これらのルーティンを整えておくことで、業務の抜け漏れや遅延を防ぐだけでなく、チーム間での連携も円滑に行えます。
ルーティンは、一人ひとりの動きを安定させ、企業全体の業務運営にもよい影響を与えます。特に繁忙期や人員の入れ替わりがあるときには、ルーティンがあることでスムーズな引継ぎや業務継続が可能になります。
ルーティンとマニュアル化の違いと関係性
ビジネスにおけるルーティンとマニュアル化は、どちらも再現性のある業務に関する言葉ですが、使われる段階が異なります。「ルーティン」は、特定の業務を日常的に繰り返し行うことですが、それを文章として整理し、全体に共有することが「マニュアル化」といえます。
ルーティンとマニュアル化は相互関係にあります。ルーティンをマニュアル化することで、ムダな工程が含まれていないか洗い出せます。また、効率的な手順をマニュアル化して共有すれば、誰でもルーティンとして定着させることができます。
ルーティン業務は同じ動作を繰り返すので、モチベーションの低下が起こりやすいのがネックです。マニュアル化すればルーティン業務の目的やゴールが明確になるので、モチベーションの低下を防ぐ効果も期待できます。
ルーティンが業務効率化にもたらす効果
ルーティンは、ただの習慣ではなく、業務全体の生産性や安定性に大きな影響を与える要素です。この章では、ルーティンが具体的にどのように業務効率化に貢献するのかを見ていきましょう。
判断や行動のスピードが上がる
業務がルーティン化されていると、一つ一つの作業にかかる判断時間が減り、すばやく行動に移せるようになります。たとえば、日報の作成や定例の資料作成など、毎回同じ手順で進められる定型業務は、あらかじめ型が決まっていることで迷いなく取り組むことができます。
また、「どこに何を記録するか」「誰に報告するか」といった細かい判断が不要になることで、営業や企画といった非定型業務への集中力を高めることにもつながります。
属人化の防止と標準化の推進
業務が特定の人にしか対応できない状態、いわゆる「属人化」は、組織のリスク要因のひとつです。しかし、ルーティンをうまく整えることで、誰が担当しても一定の成果が出せる体制が整います。
特に、次のような効果が期待できます。
- 業務の手順や基準が共有されることで、誰でも一定のクオリティで対応できる
- 急な休暇や退職、異動があってもスムーズに引継ぎができる
- 業務の進め方に迷いがなくなり、新入社員や異動者も早く戦力化できる
- ナレッジが明文化され、チーム内での学び合いが促進される
このように、ルーティンは単なる作業の反復ではなく、組織全体の「標準化の推進」において重要な要素でもあります。
ストレスの軽減とメンタルヘルスへの好影響
業務の流れがあいまいなとき、人は「これで合っているのか?」「忘れていないか?」と不安を感じやすくなります。ルーティンが整っていれば、やるべきことが明確になり、精神的な負担も軽減されます。
特に新入社員や、職場環境に慣れていないメンバーにとっては、明確なルールや手順があることで安心感が生まれ、自信を持って業務に取り組めるようになります。こうした環境は、指導者の負担減にもつながっていくので、チーム全体のメンタルヘルスにも好影響となるでしょう。
ルーティンを定着させる実践のコツ
ルーティンは自然に身につくこともありますが、ビジネスの現場で意図的に活用するには、定着させるための工夫が必要です。この章では、ルーティンを継続的に機能させるためのポイントをご紹介します。
タスクを可視化・整理する
ルーティン化の第一歩は、自分の業務を見える形で整理することです。頭の中で把握しているだけでは、抜けやムダが発生しやすくなります。紙に書き出す、タスク管理ツールを活用するなどして、「どの業務を」「どの順番で」「どれくらいの頻度で」行っているかを整理してみましょう。頻度が高く、ある程度パターンで対応できるような作業は、ルーティン化することをおすすめします。
マニュアルを活用し標準化を図る
ルーティンを定着させるためには、「やり方を決めておくこと」が欠かせません。その際に参考になるのが、マニュアルの存在です。
繰り返し行う手順や共有すべきルールがあるときには、簡単なマニュアルを作っておくとよいでしょう。業務の進め方をあらかじめ文書にしておけば、迷わず行動しやすくなり、ルーティンとして定着していきます。特に、複数のメンバーで同じ業務を行う場面や、新しい人が加わる場面では、マニュアルがあることでルーティンの共有がスムーズになります。
マニュアルによって業務の再現性を高め、ルーティンの定着を促していけば、ゆくゆくは業務の標準化にもつながるでしょう。
小さく始めて徐々に習慣化する
いきなりすべての業務をルーティン化しようとすると、継続が難しくなることがあります。まずは、取り組みやすい小さな業務から始めてみましょう。
たとえば、
- 朝のデスク整理
- 1日の予定確認
- 日報の送信タイミング など
こうした「決まった行動」をひとつずつ積み重ねていくことで、自然とルーティンとして定着していきます。
定期的に見直し・改善する
ルーティンは一度決めたら終わりではありません。業務環境や内容の変化に応じて、柔軟に見直すことが大切です。
見直しのきっかけになるタイミングとして、次のようなものがあります。
- 新しいツールやシステムを導入したとき
- 担当者や体制が変更になったとき
- 作業の所要時間や手順に変化があったとき
- チーム内で「この手順、形骸化していない?」という声が出たとき
- 月次レビューや定例ミーティングの場で振り返りを行うとき
定期的な点検とフィードバックを行うことで、時代や組織に合ったルーティンへと進化させていくことができます。
まとめ
ルーティンは、日々の業務を効率的に進めるための重要な考え方です。決まった手順を習慣化することで、迷いやムダが減り、判断や行動がスムーズになります。
属人化を防ぎ、チーム全体で安定した業務運営ができるようになるのも、ルーティンの大きなメリットです。特に、業務に慣れていない方や新しく加わったメンバーにとって、やるべきことが明確にされている環境は、安心して仕事に取り組む支えになります。
業務をルーティンとして定着させるには、マニュアルが役に立ちます。業務のタスクや手順を見直し、マニュアルとして共有することから始めましょう。マニュアルを定期的に更新することで、ルーティンの形骸化を防ぐきっかけにもなります。
フィンテックスでは、業務の棚卸や、体系整理を含めた業務マニュアル整備を承ります。興味のある方は、ぜひご相談ください。
監修者

企画営業部 営業本部長 / 経営学修士(MBA)
<略歴>
フィンテックスにて、マニュアル作成に関する様々な顧客課題解決に従事。
金融系からエンターテインメント系まで様々な経験から幅広い業務知識を得て、「分かりやすいマニュアル」のあるべき姿を提示。500社以上のマニュアル作成に携わる。また、複数の大企業でマニュアル作成プロジェクトの外部マネージャーを兼務している。
趣味は茶道。
月刊エコノミスト・ビジネスクロニクルで取材していただきました。ぜひご覧ください。
https://business-chronicle.com/person/fintecs.php
マニュアルアカデミー
最新コンテンツ

金融業務マニュアル作成のポイントと制作事例を紹介
2025.12.26
マニュアルのご相談・お問い合わせ
マニュアル作成に関するご相談やお悩みがございましたら、お気軽にお問い合わせください。
-
24時間受付中!
翌営業日にご連絡いたします。 -
資料を無料配布中!
マニュアル作成のコツを伝授します。