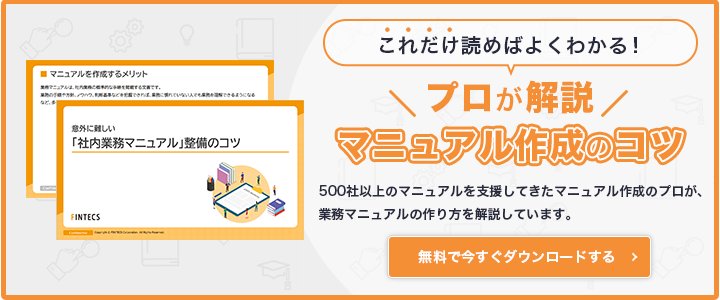-
平日9:00-18:00
- mail お問い合わせ
マニュアルアカデミー
- ホーム
- マニュアルアカデミー
- 障がい者雇用とは?知っておくべき基礎知識と業務マニュアル活用の事例を紹介
障がい者雇用とは?知っておくべき基礎知識と業務マニュアル活用の事例を紹介

企業における多様性や持続可能な社会への関心が高まるなか、障がい者雇用への取り組みはますます重要性を増しています。法的な義務にとどまらず、企業文化の成熟や組織全体の成長につながる活動として注目されています。
本記事では、障がい者雇用の基礎知識をはじめ、職場で起こりやすい課題、解決に向けた取り組みについてやさしく解説します。
フィンテックスでは、業務マニュアルを通じて障がい者雇用の現場支援を行った実績があり、その事例についても後半でご紹介します。障がい者雇用をこれから推進したいと考えている企業の方、現場での定着支援に悩んでいる方にとって、ヒントとなる内容をお届けします。
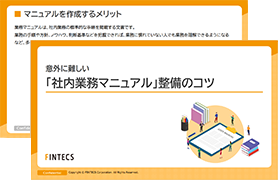
プロが解説!マニュアル作成のコツ
500社以上のマニュアルを支援してきたマニュアル作成のプロが業務マニュアルの作り方を解説しています。
目次
障がい者雇用の基本
障がい者雇用の現場で起こりやすい課題
障がい者雇用における業務マニュアルの役割
業務マニュアル作成時のポイント
まとめ
障がい者雇用の基本
障がい者雇用を進めるには、制度や対象者に関する基本的な理解が欠かせません。この章では、障がい者雇用の全体像を整理し、はじめの一歩として知っておきたいポイントを紹介します。
障がい者雇用とは何か?
障がい者雇用とは、身体障がい・知的障がい・精神障がいなどを持つ方が、その人の特性に応じた仕事に取り組めるよう、企業が働く場を提供する仕組みです。日本では「障害者雇用促進法」によって企業に雇用が義務付けられています。
2024年に施行された改正障害者差別解消法によって、合理的配慮の「努力義務」が「法的義務」に変わりました。
法定雇用率と関連制度の基礎知識
従業員が一定数以上の規模の企業には、一定割合以上の障がい者を雇用することが求められており、これを「法定雇用率」と呼びます。2025年現在、民間企業の法定雇用率は2.5%で、従業員が40人以上の企業が対象です。2026年7月から法定雇用率が2.7%に引き上げられ、対象となる企業も常時雇用労働者37.5人以上に引き下げられる予定です。
基準に満たない場合はハローワークから行政指導が行われるほか、納付金が必要になる一方、超過雇用では調整金や助成金の対象になる制度も用意されています。
企業に障がい者雇用が求められる理由
障がい者雇用は法令遵守にとどまらず、企業の社会的責任(CSR)やSDGsへの貢献という観点でも注目されています。また、異なる視点や能力を持つ人材の活躍が、組織の多様性や創造性の向上にもつながります。少子高齢化によって生産年齢人口が減少し、さまざまな業界が深刻な人材難に陥る中、人手不足の解消法のひとつとして注目されているのが障がい者雇用です。障がいの特性を理解し、それに配慮した適切な人員配置を行えば、企業にとって大きな戦力となります。
障がい者雇用における対象者の範囲
障がい者雇用の対象は、障がい者手帳を持つ方です。具体的には以下のように分類されます。
- 身体障がい者
- 知的障がい者
- 精神障がい者
- 難病患者(要件を満たす場合)
それぞれ異なる特性があるため、配慮の仕方や業務の設計も柔軟に対応することが大切です。
雇用に関する支援機関と制度の紹介
障がい者雇用にあたっては、支援機関や制度の活用が欠かせません。ハローワークや地域障害者職業センター、就労移行支援事業所などが、雇用支援や職場定着のサポートを行っています。
また、助成金制度を活用することで、企業の負担を抑えつつ雇用環境を整えることも可能です。支援機関と連携することで、より実践的な対応がしやすくなります。
厚生労働省が管轄する助成金以外にも、各自治体が提供する補助金制度が存在することがあるため、それぞれの自治体の情報を確認してみてください。
障がい者雇用の現場で起こりやすい課題
制度面の理解だけでなく、実際の現場で起こりがちな課題に対応することが、障がい者雇用の成功には欠かせません。この章では、よくある問題点とその対処法を紹介します。
ミスマッチの原因と解消法
- 個々の障がい特性を把握することが第一歩
障がい者を雇用する際は、まず本人の障がいの内容や程度を理解することが大切です。「どんな作業ができるか」「何が苦手か」を把握するために、事前のヒアリングを丁寧に行いましょう。 - トライアル雇用制度の活用も有効
実際の業務に就く前にトライアル雇用などの制度を活用することで、障がい者本人に業務適性があるかどうかを見極めやすくなります。本人の適性を見ながら、無理のない業務を任せることが可能になります。 - 採用時の業務説明は具体的に
企業側が求める業務内容と、障がい者本人が希望する業務内容にギャップがあると、不満や離職につながるおそれがあります。あらかじめ業務内容を明確にし、面接時に丁寧な説明を行うことが重要です。 - 入社後のサポート体制も重要
業務に慣れてもらうためには、障がいの特性に応じた説明や指導が欠かせません。本人の理解度に合わせた説明と、きめ細やかなフォロー体制を整えることが、長く働き続けてもらうための鍵となります。
配慮と甘えの線引きの難しさ
どこまで配慮すればよいのか迷う場面も多くあります。過剰な支援は、本人の自立を妨げる恐れもあります。
合理的配慮を基本に、本人との対話を重ねながら、働きやすさと自立のバランスを保つことが大切です。
職場定着のための支援方法
採用後の定着がスムーズにいかないケースもあります。業務内容や人間関係の不安から、早期離職につながることもあります。
定期的な面談や、業務の進捗を見える化する取り組みが効果的です。マニュアルや日報の活用も、本人の安心感につながります。
上司や同僚の理解をどう得るか
本人への配慮だけでなく、職場全体の理解も必要です。誤解や偏見を防ぐためには、上司や周囲への情報提供・研修が重要です。
障がいに対する正しい知識を共有し、誰もが働きやすい職場づくりを目指しましょう。
障がい者への指導経験の乏しさ
障がい者雇用・指導の経験が少ない企業では、雇用そのものに消極的になる傾向があります。また、雇用した場合でも、単純で簡単な作業しか任せられず、結果的に障がい者本人のやりがいや成長の機会を提供できていない、という課題がよく見られます。
障がい者雇用に取り組む企業では、ただ指導担当者に任せるのではなく、業務設計の工夫やマニュアル整備など、全社的な取り組みが必要になります。
障がい者雇用における業務マニュアルの役割
障がい者雇用を円滑に進めるためには、明確でわかりやすい業務マニュアルの整備が不可欠です。マニュアルは単なる作業手順の説明にとどまらず、安心して業務に取り組める環境づくりや、職場全体の理解を深めるツールとしても非常に重要な役割を果たします。
業務マニュアルで期待できる効果
業務マニュアルは、障がい者雇用において単なる作業手順を示すだけでなく、安心して業務に取り組める環境を整え、現場での不安を軽減し、定着と成長を支援する重要なツールです。マニュアルの整備により、担当者ごとの指示のばらつきを防ぎ、一貫した指導や指示が可能となります。
また、視覚的な手順やチェックリストの活用で業務内容の理解度や達成感を高められ、成功体験を積み重ねる土台ともなります。このように業務マニュアルは、支援側の負担軽減と職場全体の働きやすさの向上にも大きく貢献します。
マニュアルを教育・定着ツールとして活かす
マニュアルは、実際の業務だけでなく、教育や研修の場でも活用できます。
たとえば新人研修やOJTでは、教える側と教わる側が共通の資料を見ながら進めることができるため、理解の齟齬を防ぐことができます。
さらに、教える側の属人化(特定の人に業務が依存する状態)を防ぐことが可能です。企業にとっても、「誰にでも教えられる」「どの社員でも支援できる」体制を作ることで、業務が特定の人に依存せず、長期的な雇用の安定につながるでしょう。
特に障がい者就業の現場では、障がい者の特性に合わせた業務設計とマニュアルの整備が重要になります。適切なマニュアルを活用することで、教える側の負担を軽減しつつ、教わる側が安心して自立できる環境を作ることができます。
具体的な工夫として、マニュアルにメモ欄を設けることで、本人の理解度を確認したり、振り返りに活用したりすることも可能です。こうした使い方をすることで、マニュアルは単なる説明書ではなく、業務の定着をサポートする重要なツールになります。
マニュアル整備を社内全体の改善にもつなげる
障がい者雇用を機にマニュアルを整備することで、社内全体の業務改善にもつながります。業務の標準化や教育の効率化が進み、結果として誰にとっても働きやすい職場づくりに貢献します。
さらに、こうしたマニュアルは、外国人スタッフやほかの新入社員、部署異動者などへの教育にも活用できるため、社内の多様な人材への対応力を高める資産ともなります。結果として、誰にとっても働きやすい職場環境の実現につながるのです。
業務マニュアル作成時のポイント
障がい特性に合わせたマニュアル設計のポイント
障がい特性に応じたマニュアル作成において最も重要なのは、「一人ひとり異なる特性に、どう対応するか」という点であり、その核となるのが業務の“あいまいさ”を排除する工夫です。
たとえば、精神障がいや知的障がいのある方の中には、注意力が散漫になりやすかったり、忘れやすかったりする特性を持つ方がいます。このような特性がある方に対しては、業務の手順を細分化し、各ステップでの確認項目をチェックリストとしてマニュアルに明記することで、抜け漏れを防ぎ、集中を促す配慮が有効です。
また、完璧を求めすぎる傾向がある方の中には、製造業の検品作業などで品質評価を過度に厳しく判断してしまうケースも見られます。このような状況では、「98∼102% の範囲なら合格」といった許容幅の基準を明確に示し、マニュアル上でも明記する配慮が有効です。
こうした個別の特性への対応に加え、マニュアル作成時には、図や写真を多用したり、短い文でステップごとに説明したりする方法も効果的です。高圧的(威圧的)にならない「やさしい日本語」の使用や、音声ツールの活用も有効な手段となります。これらの工夫は、障がい者の理解を助けるだけでなく、結果として働く意欲や自信の向上にもつながるでしょう。
視覚的な工夫やチェックリストの活用
障がいのある方々が業務内容を円滑に理解し、安心して取り組めるようにするためには、マニュアル上の表現・形式においてさまざまな工夫を凝らすことが重要です。
口頭や文章だけでなく、視覚的なアプローチは特に有効です。たとえば、作業手順を写真や図で示すことで直感的に理解しやすくなります。また、作業のチェックリスト化は進捗を可視化し、本人が自分のペースで業務を進めることを可能にします。これにより、達成感や安心感を得ることにもつながります。
また、コミュニケーションが苦手な方にはトークスクリプトを活用することで、接客業務などにも自信を持って挑戦できるようになります。さらに、読み書きが苦手な方への配慮としては、「やさしい日本語」の使用や、図・写真を多く取り入れた構成、あるいは音声ツールの活用など、複数の方法を組み合わせたアプローチが求められます。
こうした視覚的な支援やツールの導入、多様な表現形式の工夫は、障がい者の理解度を大きく高め、ミスの防止や作業の安定化に寄与します。また、業務に対する見通しが立ちやすくなるため、障がい者が業務に安心して取り組める環境を整備することにもつながるでしょう。
実際の導入事例と業界傾向
実際にマニュアルを整備して障がい者雇用を成功させている企業も増えてきました。
たとえば、ある大手交通事業者では、一般的なマニュアルよりも余白を多く設け、障がい者を受け入れる際に企業の担当者が、その障がい者の特性に合わせて注意事項やルールを追加できる設計を導入。これにより、個々の理解の仕方に合わせて覚えられるよう工夫されました。
また、運送会社や飲食チェーンでは、精神・知的障がいを持つ方への対応を想定し、写真付きの工程マニュアルや、判断基準を明確にした手順書を活用しています。
特に障がい者雇用の多い業界には、製造業、運送業、飲食業といった、定型的かつ実作業が伴う業務が多く、個々の障がいの特性に応じた業務の切り出しや、マニュアル化による習得がしやすい環境があることが挙げられます。
まとめ
障がい者雇用は、法令対応にとどまらず、企業の姿勢や価値観を問われる重要な取り組みです。一人ひとりの特性を理解し、多様な人材が働ける環境づくりは、組織の成長にもつながります。
その支援に役立つのが、業務マニュアルの整備です。手順を明確にし、視覚的に伝えることで不安を減らし、職場での定着や活躍の促進が期待できます。マニュアルの活用は、現場の負担軽減や教育の効率化にもつながるため、職場全体の業務改善にも寄与します。
フィンテックスは、株式会社 綜合キャリアトラストと提携し、障がい者雇用のために業務を整理・分析・選定する「ソーシャルコンパス」を、共同開発しました。興味のある方は、ぜひお問い合わせください。
※参照記事:株式会社綜合キャリアトラストとのサービス共同開発について
監修者

企画営業部 営業本部長 / 経営学修士(MBA)
<略歴>
フィンテックスにて、マニュアル作成に関する様々な顧客課題解決に従事。
金融系からエンターテインメント系まで様々な経験から幅広い業務知識を得て、「分かりやすいマニュアル」のあるべき姿を提示。500社以上のマニュアル作成に携わる。また、複数の大企業でマニュアル作成プロジェクトの外部マネージャーを兼務している。
趣味は茶道。
月刊エコノミスト・ビジネスクロニクルで取材していただきました。ぜひご覧ください。
https://business-chronicle.com/person/fintecs.php
マニュアルアカデミー
最新コンテンツ

金融業務マニュアル作成のポイントと制作事例を紹介
2025.12.26
マニュアルのご相談・お問い合わせ
マニュアル作成に関するご相談やお悩みがございましたら、お気軽にお問い合わせください。
-
24時間受付中!
翌営業日にご連絡いたします。 -
資料を無料配布中!
マニュアル作成のコツを伝授します。