-
平日9:00-18:00
- mail お問い合わせ
マニュアルアカデミー
- ホーム
- マニュアルアカデミー
- 新人教育のポイントとは?大切な6つのポイントと有効な手段
新人教育のポイントとは?大切な6つのポイントと有効な手段

新人教育は、将来的に活躍してくれる社員を育てるために非常に重要です。
しかし、現場の育成担当者はさまざまな悩みを抱えています。
ここでは「新人教育のポイントを知りたい」と考えている方のため、近年の新入社員の傾向や育成担当者が抱えがちな悩み、成功のために必要なポイントなどを解説するので、ぜひ参考にしてください。
新人教育がうまくいかない理由や、効果的な対応手段についても理解できるようになります。
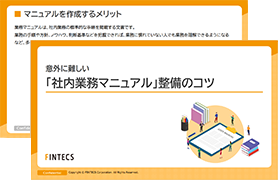
プロが解説!マニュアル作成のコツ
500社以上のマニュアルを支援してきたマニュアル作成のプロが業務マニュアルの作り方を解説しています。
新人教育の目的とは
新人教育の主な目的は、日々の業務に必要なスキルや知識を新人に習得してもらうことにあります。また、会社や業務内容について理解し、業務への意識・意欲を高めてもらうことを目指しましょう。
入社してきたばかりの新入社員は、まだ組織の文化や価値観といったものを正しく把握できていません。そういった新入社員に対し、自社で掲げている経営理念や事業方針などを理解してもらう目的もあります。
企業の一員としての意識を高める効果も期待され、新人教育は非常に重要な役割を担います。
新人教育を受けることで新入社員は業務について深く理解し、業務に対する意欲や責任を持つようになります。
新入社員の傾向
その時代によって新入社員の傾向は変わってきます。近年の新入社員にはどのような傾向があるのかを見ていきましょう。
人間関係に不安を感じている
特にコロナ禍により学生時代に対面でのコミュニケーションが十分にできなかった新入社員は、良好な人間関係を築けるか不安に感じています。
雑談をする機会が少なく、仕事で接することになる人とうまく会話ができないのではといった不安を抱えているケースもあるでしょう。
ワークライフバランスを重視する傾向も強くみられ、他の世代の人と価値観が違うのではないかといった自覚もあります。
これがさらなる人間関係の不安につながってしまうこともあるようです。
デジタル機器の操作に慣れている
Z世代の新入社員は物心ついた頃からデジタル機器と接しています。
そのため、細かいことを説明しなくてもデジタル機器の操作に慣れている人が多いという特徴があります。指導を受けることなくパソコンを使いこなせる人も珍しくありません。
ただし、人によってどこまでデジタルに詳しいかは異なるので「新入社員=デジタルネイティブ」とは考えないように注意が必要です。
積極的にキャリアアップを目指している
ワークライフバランスを重視しているというと、仕事にはそれほど前向きではないイメージを持つ方もいるでしょう。
しかし、近年の新入社員の傾向として、積極的にキャリアアップを目指していることが挙げられます。
スキルを身につけたい、専門性を高めたい、将来的には独立を目指したいなど、具体的なキャリアアップを描いている方も少なくありません。
ただ、目指すキャリアがある一方で、それをどのように実現すればよいかわからないケースもあります。
関連記事
「初心者必見!入社オリエンテーション資料作成ガイド」
育成担当者が抱えがちな悩み
新入社員を教育するにあたり、指導する立場にある人はさまざまな悩みを抱えているようです。
主な悩みは以下の3つです。
自分のタスクをこなせない
育成担当者の多くは、教育関連の業務に加えて、自身の通常業務も行うことになります。
教える時間の確保が難しいと自分のタスクをこなす時間が短くなってしまい、精神的にも体力的にも厳しく感じてしまうことでしょう。
新人教育のためにはさまざまな資料を作ったり、フィードバックなども行ったりしなければなりません。
こういった作業に対応するために自身の業務が滞ってしまう可能性もあります。
コミュニケーションがうまく取れない
新入社員と考え方が合わない、相性が悪いなどの理由から円滑にコミュニケーションをとるのが難しくなることがあります。
意思疎通が不十分だと、適切な指導はできません。
教育する側はもちろんのこと、新入社員側としても気まずさを感じてしまうようでは、なかなか教育の内容も身につかないでしょう。
また、うまくコミュニケーションが取れず質問しにくい状況ができあがってしまうと、わからないことがあっても確認を先延ばしにする癖がついてしまうことも考えられます。
新入社員によって理解や習得のペースが異なる
複数の新入社員がいる場合、それぞれ理解や習得のペースが異なります。育成担当者は個人差を正しく把握し、それぞれに適したサポートを行っていかなければなりません。
しかし、現場では多忙な通常業務と教育を両立させなければならず、十分な時間やリソースを確保できないケースも多いのが実情です。結果として、すべての新入社員に対して個別対応を行うのが難しくなってしまうのです。
また、育成担当者自身が「どう指導すればよいか」「どこまで対応すべきか」といった教育ノウハウを持ち合わせていない場合もあります。このような状況では、理解や習得が遅れている新入社員への適切なフォローが行き届かず、習熟度の差がさらに広がってしまう恐れもあるでしょう。
そのため、教育を属人的に任せるのではなく、体系的な教育フローやマニュアルの整備が求められます。
新人教育がうまくいかない例
新人教育を実践してはいるものの、なかなかうまくいかないこともあります。
特に代表的なのが以下の4つのケースです。
例①心理的安全性が担保されていない
心理的安全性とは、安心して発言・行動できる職場の空気のことをいいます。そのため、心理的安全性が十分とは言えない職場では、新入社員が「質問したら迷惑かもしれない」といった気持ちを抱えやすくなるでしょう。
その結果、わからない点を曖昧なまま放置してしまい、業務の理解が進まなかったり、同じミスを繰り返してしまったりする原因となります。
育成担当者側も「なぜ質問してこないのか」「やる気がないのでは」と誤解しやすく、信頼関係が築けないまま教育が形骸化してしまうケースもあります。
例②専門用語を多用する
新入社員のうちはまだ業界で使われる専門用語に慣れていないことから、教育する際に専門用語を多用すると理解が追いつきません。
専門用語の意味がわからないまま教育を継続しても、その後の内容を正しく理解できない可能性があります。
結果として業務にさらなる不安を感じ、早期離職にもつながります。略語についても同様です。
新入社員への教育を進めるには、専門用語の解説から必要になることを理解しておきましょう。
例③仕事の目的や背景を伝えていない
育成担当者が、業務の目的や背景を新入社員にきちんと伝えていない場合、新入社員は「なぜこの業務を行うのか」「どのような意味があるのか」を理解できず、指示された内容をただこなすだけになってしまいます。
特定の業務を教えたり任せたりする場合も、その仕事にどのような意味があるのかを伝えておくことでモチベーションの維持にもつながります。
業務のやり方だけを伝える方法では、小さな変更やトラブルへの柔軟な対応力が養われません。
例④組織の意向で仕事を丸投げする
新入社員に対し、十分な説明やサポートを行うことなく業務を丸投げしてしまう会社もあるようです。
「自由にやっていいよ」と言われても、業務に慣れていなければ効率的な進め方はもちろん、注意点もよくわかりません。丸投げの結果として業務上のミスやトラブルが発生した場合に、新入社員は叱責を受けるかもしれません。
また、企業としての教育方針や体制が整っておらず、育成担当者に丸投げする形になっている場合も注意が必要です。育成担当者が準備不足のまま指導に当たると、内容にばらつきが出たり、十分な支援ができたりせず、組織としての育成機能が機能不全に陥るリスクがあります。
新人教育に大切な6つのポイント
効率的な新人教育を行うためにも、どのようなポイントが重要なのか確認しておきましょう。以下6つのようなポイントがあります。
ポイント①仕事をしやすい雰囲気を作る
質問しにくい空気になっていたり、緊張感があったりすると、新人教育はなかなかうまくいきません。
まずは仕事をしやすい雰囲気を作ることから始めていきましょう。何かわからないことがあった際にすぐに質問できる環境を整えておくと、成長も早くなります。
「失敗してもフォローしてもらえる」と感じられるような職場づくりが求められます。
ポイント②仕事の目的や背景を伝える
仕事の目的や背景といったものを丁寧に伝えておくことにより、単なる作業ではなく、大切な業務として取り組めるようになります。また、目的を正確に理解しておくことで、状況の変化に柔軟に対応できる力が身につくはずです。
このとき、専門用語や略語などは使わないように注意しましょう。まだ現場経験の少ない新入社員でも理解できる伝え方を意識することが重要です。
ポイント③新人のステータスや目標を把握する
それぞれ得意としていることやこれまでの経験、スキルが異なるため、それらを理解した上で教育を行っていかなければなりません。新入社員の理解を深めるためには、1人ひとりのステータスや目標を把握しておきましょう。
「どこまでを教えたのか」ではなく「実際にどこまで新入社員ができているか」を把握して教育することをおすすめします。
また、本人が掲げている目標を聞き出し、それに合ったアドバイスやサポートができると、信頼関係も築きやすくなるでしょう。
ポイント④思考力を身につけさせる
本人が自分で考えられる力を身につけられるようにサポートしていくことも欠かせません。基本的な業務や考え方などを教えたら、あとは解決のヒントを与えるようにするとよいでしょう。
育成担当が細かく指導をして、指示されたことだけを行うように指導してしまうと、自発的に考えられない社員に育ってしまう恐れがあります。
ポイント⑤フィードバックを行う
行った業務などに対してよかった点や改善すべき点をフィードバックしましょう。業務を十分に理解していない段階では、失敗の原因や改善方法を自分で見出すことが難しい場合があります。
自分ではうまくいったと思っていたことでも、育成担当者には改善点が目に付くこともあるでしょう。
批判をするのではなく、論理的に失敗や業務のポイントを伝えることで今後の業務に活かしやすくなります。
ポイント⑥順序通りに進める
新人教育はあらかじめ順序を決めておき、その通りに行っていくことが求められます。突然応用的な業務を行ったり、学ぶべき順序が適切ではなかったりすると、新入社員が混乱してしまうはずです。
仕事の流れや基礎知識といったところから始め、まずは基本的な知識や手順を確実に習得させる必要があります。その上で段階的に専門的な指導につなげていきましょう。
新人教育に有効な手段
新人教育に有効な手段はいろいろありますが、中でも代表的なのがマニュアルを使った方法や、OJT、OFF-JT です。それぞれどのような手段なのかを解説します。
マニュアル
マニュアルは、新人教育を行う上でぜひとも活用したいアイテムです。新入社員が自身で確認できるマニュアルを用意しておけば、わからないことがあった際に自身で問題を解決できるようになります。
教わったことを再度聞く勇気が持てず、疑問を解消できずに業務が停滞する事態も防げます。
また、わからないことを自己解決できるようになれば育成担当者への質問も減るので、育成担当者の負担を抑える効果も期待できます。
一度マニュアルを整備すれば、長く使えるのも魅力と言えるでしょう。ただし、定期的な更新は必要です。
また、育成担当者向けのマニュアルを作成しておくこともおすすめします。育成担当者が同じマニュアルを使用することにより、育成担当者によって教える内容が違う、質が違うといった状況を防げるでしょう。
関連記事
「わかりやすいマニュアルを書くための文章作成ガイド」
フィンテックスでは、お客様のご予算に応じて「マニュアルのあるべき姿」を、さまざまな視点からご提案しています。
他社には無い、コンサルティングがフィンテックスの強みです。
お客様の現状をヒアリングし、ご希望・ご要望を伺ったうえで業務改善につなげるマニュアルを作成いたします。
詳しいマニュアル制作の実績については、以下をご覧ください。
業務マニュアル 超大型の業務マニュアル編纂プロジェクト。制作チームを編成した初動準備、さまざまなドキュメント制作の提案や柔軟な対応、20,000ページ以上のマニュアル作成、細やかなフォローなど。途中からチームを拡大し、柔軟な対応でご評価いただきました。 業務マニュアル データ形式も見た目もバラバラだったマニュアルを読みやすい構成に作り直し、写真画像の補正、印刷、製本までを一括で対応しました。現場で活用できる「使える」マニュアルになったとご評価いただきました。 OJTとは「On-the-Job Training」の略語で、実際の仕事現場で業務を体験しながら学んでいく方法のことをいいます。 業務内容や手順を座学で学び、その場では理解できた気がしても、現場でいきなり業務を実践するのは困難です。そういった場合でもOJTならば現場で仕事をしながら学べるため、習得が早いのが魅力です。 ただし、OJTの実施だけでは新人教育として不十分なケースも少なくありません。新入社員はまだ基礎知識や業務全体の流れを理解できていないため、いきなり現場に出されても業務の意味や目的を理解できず、戸惑ってしまうことがあります。 OJTは単独で機能させるのではなく、あらかじめ基礎を座学やマニュアルで学ばせた上で、計画的かつ段階的に取り入れていくことが重要です。育成担当者が進捗を把握しながら、定期的にフィードバックを行うことで、より効果的な育成が可能になります。 OFF-JTとは「Off-the-Job Training」の略語で、実際に業務を行う現場以外で行われる教育のことです。 たとえば、社内研修や外部セミナー、オンライン上で学べるe-ラーニングなどが挙げられます。体系的に学べるだけではなく別部署や他社の社員と交流する機会が持てるので、何かあった際に相談相手になってくれる仲間が見つかることもあるでしょう。 OFF-JTは、実務を通して学ぶのが難しいコンプライアンス教育やハラスメント研修にも活用されています。 いかがだったでしょうか。新人教育を行う上で押さえておきたいポイントについて解説しました。育成担当者が抱えがちな悩みや、対策についてもご理解いただけたかと思います。 新人教育がうまくいかない状況が続いてしまうと、新入社員が十分に力を発揮できず、業務への不安や不満から早期離職につながる恐れがあります。こうした離職が増えることで、結果的に組織全体の生産性に悪影響を及ぼす可能性があります。 このような事態を防ぐためにも、教育体制を整え、誰が担当しても一定の質で教えられるようなマニュアルの整備が重要です。マニュアルを活用することで、新入社員が自ら学べる環境が整い、育成担当者の負担も軽減できます。 しかし、マニュアルはただ作成すればいいわけではありません。本当に活用されるマニュアルを作ることが求められます。 自社での対応が難しい場合は、これまで多くのマニュアル作成実績を持つフィンテックスにご相談ください。新人教育にも活用できるマニュアルの提案・作成にも対応いたします。 監修者 企画営業部 営業本部長 / 経営学修士(MBA) <略歴> フィンテックスにて、マニュアル作成に関する様々な顧客課題解決に従事。
金融系からエンターテインメント系まで様々な経験から幅広い業務知識を得て、「分かりやすいマニュアル」のあるべき姿を提示。500社以上のマニュアル作成に携わる。また、複数の大企業でマニュアル作成プロジェクトの外部マネージャーを兼務している。
趣味は茶道。
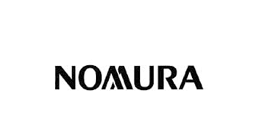

OJT
OFF-JT
使いやすいマニュアルを整備しておくのがおすすめ

月刊エコノミスト・ビジネスクロニクルで取材していただきました。ぜひご覧ください。
https://business-chronicle.com/person/fintecs.php
マニュアルアカデミー
最新コンテンツ

金融業務マニュアル作成のポイントと制作事例を紹介
2025.12.26
マニュアルのご相談・お問い合わせ
マニュアル作成に関するご相談やお悩みがございましたら、お気軽にお問い合わせください。
-
24時間受付中!
翌営業日にご連絡いたします。 -
資料を無料配布中!
マニュアル作成のコツを伝授します。








