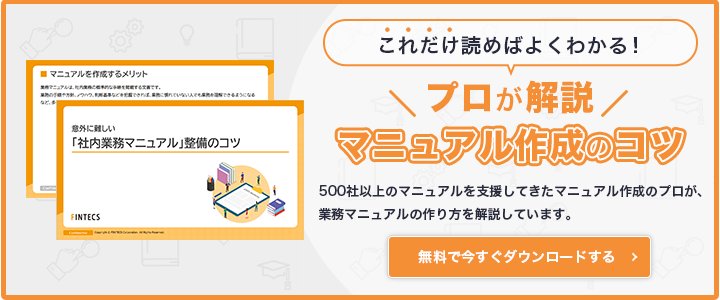-
平日9:00-18:00
- mail お問い合わせ
マニュアルアカデミー
- ホーム
- マニュアルアカデミー
- カスタマーハラスメント(カスハラ)とは? クレームとの違いや企業が取るべき対策方法を解説
カスタマーハラスメント(カスハラ)とは? クレームとの違いや企業が取るべき対策方法を解説

近年、社会問題として注目されるようになった「カスタマーハラスメント(カスハラ)」をご存じでしょうか。カスハラは、単なるクレームとは異なり、従業員に対して過度な要求や精神的な負担を強いる深刻な問題です。企業にとっても、従業員の離職やメンタル不調、さらにはブランドイメージの低下といったリスクにつながるため、適切な対策が求められています。
本記事は、カスハラとは何かをわかりやすく整理し、企業が取るべき対策方法について詳しく解説します。特に、従業員や事業を守るための業務マニュアル整備や、研修テキスト活用にも触れ、すぐに実践できるポイントをご紹介します。
カスハラ対策をこれから強化したいと考えている企業の担当者の方や、現場の従業員教育を見直したいと考えている方は、ぜひ参考にしてください。
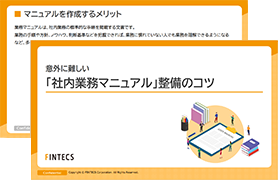
プロが解説!マニュアル作成のコツ
500社以上のマニュアルを支援してきたマニュアル作成のプロが業務マニュアルの作り方を解説しています。
目次
カスタマーハラスメント(カスハラ)とは
カスハラが企業にもたらす影響
企業が取るべきカスハラ対策とは
まとめ
カスタマーハラスメント(カスハラ)とは
日本では、かつては「お客様は神様」とされてきた文化もありましたが、近年では顧客による過度な言動がカスタマーハラスメント(以下カスハラ)として社会問題化し、注目されるようになりました。ここでは、カスハラの定義やクレームとの違い、社会的に問題視されるようになった背景について解説します。
カスハラの定義と代表的な事例
カスハラとは、顧客という立場を利用し、従業員に対して常識を越えた対応を強要したり、人格を否定するような発言をしたりする行為を指します。明確な法的定義はないものの、多くの企業では「業務の適正な範囲を逸脱する不当な言動」として、社内ガイドラインなどで整理されています。
代表的なカスハラの事例には、次のようなものがあります。
- 長時間にわたる苦情や要求の繰り返し
- 威圧的な態度や怒鳴り声、暴言
- 無償対応を過度に求める
- 土下座の強要
- SNSでの名誉毀損やレビューへの嫌がらせ
これらは、従業員の心身に大きなストレスを与えるだけでなく、職場全体の雰囲気やサービス品質にも悪影響を及ぼします。
クレームとの違い
企業にとって重要なのは、正当なクレームとカスハラを明確に区別することです。
クレームは、サービスや商品に対する正当な意見や要望を伝える行為であり、企業にとってはサービス改善のチャンスでもあります。一方、カスハラはその目的を逸脱し、従業員を萎縮させるような行為を含んでいる点が特徴です。
たとえば、「商品に不備があったので返品したい」という要望はクレームです。しかし、「馬鹿野郎」といった暴言や、「今すぐ土下座しろ」といった要求は、商品への要望や意見から逸脱しているので、カスハラに該当します。対応の線引きを明確にしておくことで、現場の従業員が適切に行動できるようになります。
クレーム対応業務をマニュアル化することで得ることができるメリットについて詳しく知りたい方はこちら
関連記事:トラブル対応業務でマニュアルを準備しておく効果とメリットは?
カスハラが社会問題化している背景
カスハラが社会問題として注目されるようになった背景には、サービス業の現場における過剰な「顧客第一主義」や、SNSの普及による炎上リスクの高まりなどがあります。近年では「カスハラ」という言葉がメディアでも頻繁に取り上げられるようになり、企業側も対応を求められる場面が増えています。
また、働き方改革の流れの中で、一人ひとりの従業員を守る企業姿勢が重要視されており、「カスハラから従業員を守るためにどうするか?」という視点での取り組みが求められています。
このような背景から、業務マニュアルの整備やお客様への対応研修の実施など、具体的な防止策や対応策が企業にとって急務となっているのです。
カスハラが企業にもたらす影響
カスハラは個人の問題ではなく、企業全体にとって深刻な影響を与えるリスクです。従業員のメンタルヘルスや職場環境、企業イメージにも悪影響を及ぼす可能性があり、放置すれば離職率の上昇や顧客対応力の低下にもつながります。ここでは、企業が認識すべき具体的な影響について見ていきましょう。
従業員の離職や精神的ダメージ
カスハラの被害を受けると、従業員は強いストレスや不安を感じるようになります。中には不眠や体調不良に陥ったり、仕事への意欲を失ったりしてしまうケースも少なくありません。この状態が続けば、人材の定着や育成にも大きな支障をきたし、最悪の場合は離職につながる恐れもあります。
職場全体への悪影響
カスハラの影響は被害を受けた本人だけにとどまりません。カスハラ対応に人手が割かれることで、フォローに回る他の従業員の負担が増加し、他のお客様対応に支障が出る可能性があります。
また、会社として、カスハラへの適切な対応方針や対応策を決めていないと、「会社は守ってくれない」という印象を従業員に与えてしまい、労働意欲の低下や会社への不信感につながる恐れがあります。
企業ブランドや信頼性への損失
カスハラへ適切な対応を取らないと、SNSや口コミで一気に広がり、炎上してしまう恐れがあります。ときには、被害者であるはずの従業員の対応ばかりが注目され、企業イメージの低下を招いてしまうこともあります。
逆に、適切な対応を行っている企業は「従業員を大切にする会社」という好印象を与えることができます。これにより、信頼性の高い企業としてユーザーからの評価も向上します。ブランド価値を守るという意味でも、経営視点でも、カスハラ対策は無視できないテーマなのです。
企業が取るべきカスハラ対策とは
カスハラの発生を防ぎ、万一発生した際にも適切に対応するためには、企業としての明確な姿勢と仕組みづくりが欠かせません。対応の属人化を避けるためにも、ガイドラインの整備や研修制度の構築が重要です。ここでは、企業が実践すべき4つの具体的な対策をご紹介します。
明確な方針とガイドラインの策定
まず重要なのは、「カスタマーハラスメントを許容しない」という企業方針を社内外に明示することです。対応方針や判断基準をガイドラインとしてまとめ、現場の従業員が自信を持って行動できる環境をつくりましょう。
ガイドラインに載せる文書は、以下のようなものがあります。
- カスハラの定義と具体例
- 従業員が対応を拒否できる基準
- 上司や専門部署へのエスカレーション手順
- 被害報告の受付方法
ガイドラインは業務マニュアルと連動させて、日常業務の中で活用できる形にしておくことがおすすめです。
従業員への研修・教育の実施
ガイドラインを整備するだけでは十分ではありません。実際の対応方法を体得するには、研修による教育が不可欠です。
研修では、以下のようなテーマを取り上げると効果的です。
- カスハラが発生する背景・要因
- カスハラの事例とリスク理解
- 初期対応時の言葉遣いや姿勢
- チームとしての連携方法
一人ひとりの対応力を高めていけば、現場の従業員の負担が軽減されるだけでなく、お客様との健全な関係づくりにも役立ちます。動画教材や対応マニュアルとセットで実施することで、より実践的な研修が可能になります。
業務マニュアル・対応フローの整備
カスハラ対応を現場任せにしないためには、誰が、どのように、どのタイミングで動くかを明示した業務マニュアルの整備が有効です。具体的には以下のようなものが挙げられます。
- カスハラ発生時の初期対応フロー
- 担当者別の役割と連携手順
- 上長・専門部署への報告ルート
- 記録用フォーマットや報告書サンプル
カスハラ対応は、個人の判断では難しいものが多く、対応によっては従業員が危険にさらされるリスクがあります。従業員を守るためにも、あらかじめ行動方針や対応フローを明示し、日常業務に組み込んでいくことが大切です。また、マニュアルによって対応方法を社内共有し、企業全体でカスハラに対応していくという意識を持つことが重要です。
業務マニュアルを作成するメリット・デメリットについてもっと知りたい方はこちら
関連記事:マニュアルとは何?概要や作成するメリットデメリットを紹介
関連記事:マニュアル作成における「初校」「2校」「念校」って何?
相談・フォロー体制の構築
カスハラの被害に遭った従業員が、安心して声を上げられる環境をつくることも大切です。相談窓口の設置や、メンタル面のフォロー体制を社内に整えておくことで、被害の早期把握と対処が実現できます。
具体的には、次のような仕組みが考えられます。
- 社内ヘルプデスクの設置
- 面談やメンタルケアの提供
- 匿名での通報手段
- 対応後のフィードバック共有
こうした仕組みが従業員の孤立を防ぎ、所属する企業への信頼にもつながります。
フィンテックスでは、お客様のご予算に応じて「マニュアルのあるべき姿」を、さまざまな視点からご提案しています。
他社には無い、コンサルティングがフィンテックスの強みです。
お客様の現状をヒアリングし、ご希望・ご要望を伺ったうえで業務改善につなげるマニュアルを作成いたします。
詳しいマニュアル制作の実績については、以下をご覧ください。
業務マニュアル 超大型の業務マニュアル編纂プロジェクト。制作チームを編成した初動準備、さまざまなドキュメント制作の提案や柔軟な対応、20,000ページ以上のマニュアル作成、細やかなフォローなど。途中からチームを拡大し、柔軟な対応でご評価いただきました。 業務マニュアル データ形式も見た目もバラバラだったマニュアルを読みやすい構成に作り直し、写真画像の補正、印刷、製本までを一括で対応しました。現場で活用できる「使える」マニュアルになったとご評価いただきました。 カスタマーハラスメント(カスハラ)は、従業員の心身に深刻なダメージを与えるだけでなく、企業全体の生産性や信頼性を損なうリスクを含んでいます。適切に対策を講じていけば、従業員を守るばかりではなく、組織としての健全な成長を促進できるでしょう。 企業が行うべきカスハラ対策としては、以下の4つが大きな柱となります。 これらを実行することで、一人ひとりの従業員が安心して働ける環境が生まれ、顧客対応にも一貫性と信頼性が生まれます。 フィンテックスでは、こうした課題に対応する「カスハラ対応マニュアル」や「クレーム対応研修用テキスト」の制作も承っております。カスハラ対策の一環として、実務に即したマニュアルの整備をご検討の際は、ぜひお気軽にご相談ください。 つい読んでしまうマニュアル作成のリーディングカンパニー、株式会社フィンテックス 監修者 企画営業部 営業本部長 / 経営学修士(MBA) <略歴> フィンテックスにて、マニュアル作成に関する様々な顧客課題解決に従事。
金融系からエンターテインメント系まで様々な経験から幅広い業務知識を得て、「分かりやすいマニュアル」のあるべき姿を提示。500社以上のマニュアル作成に携わる。また、複数の大企業でマニュアル作成プロジェクトの外部マネージャーを兼務している。
趣味は茶道。
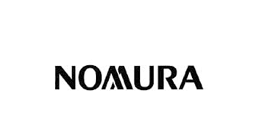

まとめ

月刊エコノミスト・ビジネスクロニクルで取材していただきました。ぜひご覧ください。
https://business-chronicle.com/person/fintecs.php
マニュアルアカデミー
最新コンテンツ

金融業務マニュアル作成のポイントと制作事例を紹介
2025.12.26
マニュアルのご相談・お問い合わせ
マニュアル作成に関するご相談やお悩みがございましたら、お気軽にお問い合わせください。
-
24時間受付中!
翌営業日にご連絡いたします。 -
資料を無料配布中!
マニュアル作成のコツを伝授します。