-
平日9:00-18:00
- mail お問い合わせ
マニュアルアカデミー
- ホーム
- マニュアルアカデミー
- 業務効率化の方法とは?実施するメリットと具体的な手順を確認
業務効率化の方法とは?実施するメリットと具体的な手順を確認

生産性向上のために実施していきたいのが、業務効率化です。
ただ「手間やコストがかかりそうでできずにいる」「具体的な方法がわからない」というケースもあるでしょう。
そこで、業務効率化に取り組みたいと考えている方のため、具体的な方法について解説します。この記事を読むことで実施する際の手順や自社で取り入れたいアイデアなどが見えてくるようになるので、ぜひご覧ください。
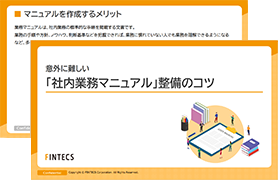
プロが解説!マニュアル作成のコツ
500社以上のマニュアルを支援してきたマニュアル作成のプロが業務マニュアルの作り方を解説しています。
業務効率化とは
業務効率化とは、現在行っている業務の中からムリやムダ、ムラを洗い出し、業務の工程を見直したり改善したりすることをいいます。業務の流れを見直すほか、自動化・ITツールの導入、人員配置の変更など、方法は実にさまざまです。
日本は少子高齢化が進んでおり、今後、さらに働き手は不足していくと予想されています。限られた人員の中で業務に取り組んでいかなければならないケースも増えており、多くの企業において業務効率化が求められていると言えるでしょう。
業務効率化を図ることで、企業全体の生産性を向上させるだけではなく、組織の強化にもつながります。特に現在業務の効率化ができていないと実感している場合は力を入れていきましょう。
関連記事
「業務標準化とは?得られる効果や成功させるためのポイント」
業務効率化のメリット
業務効率化に取り組むことにより、どのような変化が期待できるのでしょうか。以下のようなメリットがあります。
時間的コストを削減できる
業務効率化を行うことで、これまで時間をかけていた非効率な作業や手間を見直すことができます。
同じ業務でもムリ・ムダ・ムラをなくすことにより、より短時間で処理できるようになり、業務時間全体の短縮につながります。
その結果として、残業が発生しにくくなり、社員のワークライフバランスの改善や、企業側にとっては残業代などの人件費削減といったコスト面のメリットも期待できます。
また、業務効率化のためにデジタルツールを用いれば、ヒューマンエラーが減るのもメリットです。
生産性が向上する
生産性向上のためにも業務効率化が欠かせません。不要な手作業や重複作業が削減されることになるので、その他の業務に時間を充てられるようになります。
限られた時間内でこなせる業務量が増えるため、組織全体の生産性が向上するでしょう。業務の進行スピードが単純に速くなるだけではなく、業務の質も安定しやすくなります。
社員のモチベーション向上につながる
業務効率化は、単に無駄な作業を減らすだけではなく、働きやすい環境を整える取り組みでもあります。たとえば、業務フローの見直しによって作業の進め方が明確になったり、ツールの導入で作業負担が軽減されたりすると、社員のストレスや不安が減少し、日々の業務に集中しやすくなります。
また、属人化の解消や業務マニュアルの整備により、「何をすべきか」「どう進めればよいか」が明確になれば、迷いや戸惑いも減り、仕事に対する自信や達成感を得られやすくなります。
こうした前向きな環境づくりが、社員のモチベーション向上につながり、結果として職場への満足度や定着率の向上、チームワークの強化にもつながるでしょう。
業務効率化を図る方法
実際にどういった形で業務効率化を進めていけばいいのでしょうか。ここでは全体の手順を6つに分けて解説していきます。
手順①業務内容の現状を把握する
はじめに業務の棚卸しを行い、現在自社やチームがどういった業務に取り組んでいるのか詳細に洗い出します。
各業務で求められるスキル・経験などもまとめておきましょう。
業務フローを図にしたり、業務ごとの時間を記録したりしておきます。具体的な業務内容の把握を行うためには、担当者へのヒアリングも実施しましょう。
手順②問題点や課題を洗い出す
どのような問題点・課題があるのかを洗い出していきます。
手順①で把握した業務内容を可視化することで、重複している業務や、不要な作業が見えてくるでしょう。
業務の停滞を招いている原因(ボトルネック)を特定することも重要です。
業務内容を把握する際と同様に、実際に業務を行っている担当者からのヒアリングも大切です。
手順③改善すべき箇所の優先順位を決める
改善すべき部分が見えてきたら、どのポイントから優先的に業務改善に取り組んでいくのか考えます。
洗い出しを行った結果、複数の問題点や課題が見つかることもあるでしょう。しかし、それらに対し、同時に改善策を実施していくのは現実的なことではありません。
改善によって削減できる工数や、その問題・課題の改善によりどの程度の業務効率化が可能か判断し、どこから着手するか決めることになります。
手順④適した改善方法を決める
課題や問題を解決するために適した方法を検討します。
たとえば、アナログ作業をシステムで自動化する、複数の業務をまとめるなど、選択肢はさまざまです。
具体的な改善方法を決める際は、現場の声も重視しましょう。業務の担当者に相談をしながら改善方法を決定していくと、現場で本当に役に立つ施策につながります。
手順⑤業務改善策を実施する
決定した改善方法を実際に導入していきましょう。
実際に改善策を実施するのは現場の担当者なので、現場の混乱を防ぐため、担当者への説明や教育、ツールの準備を十分に行う必要があります。
準備期間を十分にとり、担当者と情報を共有しながら業務改善策を実施していきます。
手順⑥実施後の効果検証を行う
業務改善を実施したらそれで終わりとしてしまうのではなく、その効果を検証していきましょう。目標に対しどの程度改善されたのか、予想外の問題は起きていないかなどを評価していきます。
その結果をもとに再調整が必要になることもあるでしょう。PDCAサイクルを回しながら業務の分析と改善、検証を繰り返していきます。
業務効率化を促進するアイデア
業務効率化のために取り組める方法は数多く存在します。ぜひ実践してほしいアイデアを紹介していくので、自社に適したものを探してみてください。
業務マニュアルを用意する
業務マニュアルを整備することで、作業手順や業務の進め方を誰でも把握できるようになります。担当者による対応のばらつきを防ぎ、一定の品質で業務を遂行できるため、作業効率や業務品質の安定化に効果的です。
また、業務の属人化を防ぐ上でもマニュアルは有効であり、新人教育や業務の引き継ぎにも活用できます。結果として、日々の業務負担の軽減や、業務全体のスピードアップにもつながります。
そのため、自社の業務内容に応じた実用的なマニュアルを用意しておくことが重要です。
関連記事
「マニュアル作成の目的とは?作成のコツとともに紹介」
フィンテックスでは、お客様のご予算に応じて「マニュアルのあるべき姿」を、さまざまな視点からご提案しています。
他社には無い、コンサルティングがフィンテックスの強みです。
お客様の現状をヒアリングし、ご希望・ご要望を伺ったうえで業務改善につなげるマニュアルを作成いたします。
詳しいマニュアル制作の実績については、以下をご覧ください。
業務マニュアル 超大型の業務マニュアル編纂プロジェクト。制作チームを編成した初動準備、さまざまなドキュメント制作の提案や柔軟な対応、20,000ページ以上のマニュアル作成、細やかなフォローなど。途中からチームを拡大し、柔軟な対応でご評価いただきました。 業務マニュアル データ形式も見た目もバラバラだったマニュアルを読みやすい構成に作り直し、写真画像の補正、印刷、製本までを一括で対応しました。現場で活用できる「使える」マニュアルになったとご評価いただきました。 全体的な業務の流れを明確にしておくことで業務効率化が可能です。1日を通してどういった業務を行うのか、どのような流れで進めるのかなどをわかりやすくフローチャートでまとめておきます。 業務の流れを図式化することにより、全体のプロセスを視覚的に把握しやすくなるはずです。 できる限り、業務の統合や廃止に力を入れていきましょう。 たとえば、現在行っている業務の中で何のために行っているのか、どういった効果があるのか不明な業務はないでしょうか。使われるかわからない資料を作成したり、1回で済む確認作業を何回も行っていたりする場合はこれらを廃止しましょう。 また、ひとつにまとめられるものがあれば統合することで業務を凝縮し、作業時間を抑えられます。 定期的に「この業務は本当に必要か」を確認していくことで統合・廃止できる業務に気づきやすくなるでしょう。 業務効率化を進めるには、まず日々の業務の中で「どの業務から着手すべきか」を見極めることが重要です。優先順位を明確にすることで、限られた時間やリソースを本来注力すべき重要業務に集中させることができます。 特に、難易度が高かったり、時間がかかったりする業務は後回しにすると対応が間に合わなくなる可能性があるため、タスク管理ツールなどを活用して計画的に取り組みましょう。 一方で、短時間で済む簡単な作業を先に終わらせようとすると、気づかないうちに重要業務への着手が遅れてしまうことがあります。時間がかからない業務は、隙間時間やメイン業務の合間にこなすなど、業務の性質に応じてバランスよく取り組むことがポイントです。 可能な範囲で自動化を試みましょう。人の手で行わなくてもツールを使用することで自動化できるものは自動化してしまった方が素早く、ミスなく対処できるようになります。 データ入力やメールの送信、請求書の処理などは時間がかかることに加えて、ミスも発生しやすい業務です。これらはRPAと呼ばれる業務の自動化テクノロジーが得意とする部分でもあるので、積極的に導入を検討してみてはいかがでしょうか。 人間の判断が不要な作業については自動化が適しています。 会社には、これまで積み重ねてきたデータベースがあるかもしれません。まだデータベースを導入していない場合は導入を検討していきましょう。 顧客情報や過去の業務履歴、寄せられたクレームなどをデータベース化してまとめておくことにより、必要な情報を必要なときに素早く取り出すことが可能です。同様のトラブルに対して過去はどのように対応したのか、寄せられた質問にどういった回答を行ったのかなども振り返りやすくなります。 一度に大量の業務を行うと集中力が低下しやすくなり、ミスの原因にもなります。業務を複数日に分散させましょう。 たとえば、資料を30種類作る場合、それらをまとめて対応しようとすると作る側もチェックする側も大変です。しかし、1日に10種類ずつ、3日間かけて対応すれば、お互い小さな労力で済みます。 集中力が維持しやすくなり、作業の質を向上させることにもつながるでしょう。 担当者の配置に問題がある場合は、それを見直すことによって業務の効率化につながります。担当者の配置を考える際は、スキルと経験をもとにして慎重に検討しなければなりません。 ただ、実際に配置してみた後に担当者が適切ではないことに気づくケースもあるでしょう。誰でも得手不得手があるので、現場の状況に応じて担当の変更も検討することが大切です。 作業スピードを向上させることは、直接的な業務効率化につながります。もちろん、ただ速いだけでミスが多ければ問題ですが、品質を保ちながらできる範囲で作業のスピードアップを図りましょう。 【スピードアップにつながる一例】 ひとつひとつは小さなことであっても、年単位で見ると大きな効果をもたらすことも珍しくありません。 アイデアは複数組み合わせて実践していきましょう。 たとえば、不要な業務は廃止し、自動化可能なところはツールを活用、優先度を決めた上で業務に取り組むといった形です。 ひとつのアイデアのみを実践するのと比べて大幅に業務効率化が期待できます。アイデアの組み合わせ方によっては相乗効果が生まれることもあるので、どういったアイデアを掛け合わせていくかもよく検討してみましょう。 おすすめの業務効率化のアイデアを紹介してきました。これらを成功に導くためには、以下の3つが大切です。 どの業務をどのように効率化したいのか明確にしておきましょう。効率化すること自体が目的ではないため、何をどのように改善させたいのかといった、その先を考えることが重要です。 目的が曖昧なまま行ってしまうと、なかなか効果的な施策につながりません。 たとえば「在庫管理のミスが多い」のように、具体的な業務と課題を特定しておきます。課題を特定することでどこを効率化すべきかが見えてくるはずです。 マニュアルが整備されていない、あるいは機能していない場合は、業務マニュアルの見直しや新規作成を検討しましょう。たとえば、「マニュアルそのものが存在しない」「内容が古く、現場の業務実態と一致していない」「必要な情報が十分に記載されていない」といった状況では、現場で業務の質にばらつきが出る恐れがあります。 属人化している業務や、担当者によって成果物の品質に差がある業務は、特にマニュアル化の優先度が高いと言えます。誰が担当しても一定の品質で業務を遂行できるようにすることで、業務効率と安定性の両面を高めることができます。 フォーマットを活用し、報告書や見積書といったものの形式のほか、フォントサイズ、名前の付け方などを統一しておくのもよいでしょう。 デザイン面に関しても同様です。 全体的な規格を統一しておくことで、差し替えや修正などをする際にもどのような形で対応するべきかわかりやすくなります。 いかがだったでしょうか。業務効率化を図る方法について解説しました。 実施することでどういったメリットがあるのか、どのようなことを押さえておけばよいのかもご理解いただけたでしょう。 業務のムリ・ムダ・ムラを減らし、業務の進め方を整えることは、単に作業時間を短縮するだけでなく、社員が安心して仕事に集中できる「働きやすい職場環境」の構築にもつながります。 こうした取り組みは、担当者個人の工夫だけでは限界があるため、組織全体で計画的に進めていくことが重要です。 特に、業務マニュアルや操作マニュアルが整備されていない場合は、業務効率が悪くなってしまう恐れがあります。フィンテックスでは、現場で本当に活用されるマニュアル作成を得意としているので、ぜひご相談ください。 監修者 企画営業部 営業本部長 / 経営学修士(MBA) <略歴> フィンテックスにて、マニュアル作成に関する様々な顧客課題解決に従事。
金融系からエンターテインメント系まで様々な経験から幅広い業務知識を得て、「分かりやすいマニュアル」のあるべき姿を提示。500社以上のマニュアル作成に携わる。また、複数の大企業でマニュアル作成プロジェクトの外部マネージャーを兼務している。
趣味は茶道。
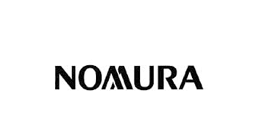

業務フローチャートを作成する
業務を統合・廃止する
業務の優先順位を設定する
自動化を試みる
データベースを有効活用する
業務を複数回に分散させる
業務の担当者を変える
作業のスピードアップを図る
さまざまなアイデアを組み合わせる
業務効率化のアイデアを成功に導くためのポイント
ポイント①効率化を行いたい項目を明確化する
ポイント②マニュアルを作成して業務のクオリティを均一化する
ポイント③資料の規格を統一する
働きやすい職場づくりにもつながる

月刊エコノミスト・ビジネスクロニクルで取材していただきました。ぜひご覧ください。
https://business-chronicle.com/person/fintecs.php
マニュアルアカデミー
最新コンテンツ

金融業務マニュアル作成のポイントと制作事例を紹介
2025.12.26
マニュアルのご相談・お問い合わせ
マニュアル作成に関するご相談やお悩みがございましたら、お気軽にお問い合わせください。
-
24時間受付中!
翌営業日にご連絡いたします。 -
資料を無料配布中!
マニュアル作成のコツを伝授します。








