-
平日9:00-18:00
- mail お問い合わせ
マニュアルアカデミー
- ホーム
- マニュアルアカデミー
- 人材育成の課題とは?解決のために押さえておきたい8つのポイント
人材育成の課題とは?解決のために押さえておきたい8つのポイント

企業の中には、人材育成に課題を抱える企業も少なくありません。
抱えている課題によっては「人材育成が滞っている」「実施してはいるものの効果は低い」という事態につながることもあります。
具体的な課題は企業によって異なりますが、できるだけ早い段階で解決策を見出し、効率的に取り組んでいかなければなりません。
本記事では人材育成における主な課題や、解決策を解説していきます。
具体的に何を実践していけば効率的な人材育成につながりやすくなるのかがわかるようになるので、ぜひご覧ください。
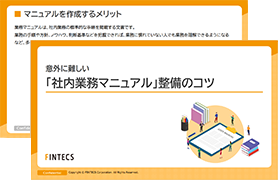
プロが解説!マニュアル作成のコツ
500社以上のマニュアルを支援してきたマニュアル作成のプロが業務マニュアルの作り方を解説しています。
人材育成とは?
そもそも企業において人材育成とは、企業が収益を上げたり、経営を推進したりするために必要な力を従業員が得られるように育成していくことをいいます。
具体的にどのような力を育成していくかは企業によって異なるので、自社の業務に必要な知識・スキルを正確に把握して育成する必要があります。
一般的なスキルだけではなく、専門的なスキルを磨くことも重要です。
能力を高めていくためには1人ひとりの従業員の努力も求められますが、人材育成に関しては企業側が主導する形で取り組んでいくことになります。
企業の成長や持続的成功に直結する重要な要素です。
関連記事
「社内教育とは?代表的な方法と効率的に行うためのポイント」
人材育成の必要性
人材育成はなぜ必要なのでしょうか。
重要とされている理由は、主に生産性の向上と社員の定着率向上のためです。
それぞれ解説します。
生産性の向上
近年、多くの企業が人手不足という課題に直面しています。
このような状況の中で、限られた人員で成果を上げるためには、社員1人ひとりの知識・スキルの向上が不可欠です。
人材育成を通じて業務に必要なスキルや知識を習得し、実務を通して経験を積むことで、社員の業務遂行能力は着実に高まります。
こうした育成と経験の積み重ねによる相乗効果によって、パフォーマンスが向上し、結果的に生産性の底上げが期待できます。
また、社員のスキルが全体的に底上げされることで、業務の効率化や属人化の解消にもつながります。
特に、日本は少子高齢化に伴う労働力の減少が問題となっており、今後も人手不足の傾向が続く見込みです。
人手不足に悩む企業では、人材育成による生産性向上がさらに求められることでしょう。
社員の定着率の向上
社員の定着率を向上させる効果も期待できます。
離職の理由は人それぞれではありますが、仕事にやりがいを感じられないことや成長できないこと、正しく評価されないことなどが離職の大きな要因になっています。
人材育成を行うことで会社への愛着や信頼などのエンゲージメントが高まれば、離職を防ぐことが可能です。
適正な育成を行うことで「育ててもらっている」「期待されている」といった気持ちにもつながります。
定着率が低い会社は求職者に敬遠される可能性があるため、人材採用の場面でも、離職率の低さは大きなアピールポイントになります。
関連記事
「新人教育のポイントとは?大切な6つのポイントと有効な手段」
人材育成における課題
多くの企業では人材育成に関して少なからず課題を抱えているようです。
ここでは、抱えやすい課題を6つ紹介します。
課題①人材育成に充てる時間の確保が難しい
日常業務に追われている企業では、研修やOJTに充てる時間を確保できず、人材育成が後回しになるケースが多いです。
特に、人員が限られている中小企業や零細企業の場合、育成できる人材が限られており、時間が十分にとれないこともあるでしょう。
しかし、生産性や社員の定着率向上を図る上でも、育成への投資は避けて通れません。
そのためには、育成担当者の業務負担を軽減するなど、企業全体で育成に向き合う体制づくりが求められます。
直接の指導が難しい場合は、e-ラーニングや外部セミナーなども活用していきましょう。
課題②社内に人材育成の知識やスキルがない
人材育成のためには専門的な知識や指導のノウハウが求められます。
必要なスキルをもった育成担当者がいないことを課題として感じている企業も多いようです。
また、育成担当者として不適切な人に無理やり任せることで、指導力不足を招く恐れがあります。
結果的に期待していたほどの成果が得られず、時間やコストばかりが高くついてしまうこともあります。
企業としては育成を行う側のスキルアップにも力を入れていかなければなりません。
課題③社員が人材育成の重要性を理解できていない
育成を行う立場である担当者が、人材育成の重要性を理解できていないと、効果的な育成はできません。
たとえば「人材育成を行うのは会社の方針だから」と考えてしまうと、なかなか身が入らないこともあるでしょう。
結果として中身のある育成ができず、育成されている側としても前向きに取り組めない場合があります。
人材育成を行う目的や意味がきちんと共有されないままで育成を始める場合に起こりやすい問題です。
課題④育成される社員の意欲が低い
育成を受ける社員本人の成長意欲が低ければ、どれだけ効果的な人材育成を行ったとしても十分な成果にはつながりません。
特に、育成される側が常に受け身の状態になってしまうような育成は、モチベーションの低下にもつながるので注意しましょう。
意欲を引き出すためにはどのような工夫が必要かなどを考えた上で取り組んでいくことが求められます。
育成を始める前にどのような目的があるのか、どういった効果が期待できるのかなどを伝えておくと前向きに取り組みやすくなるはずです。
課題⑤計画的に実施できていない
事前に育成に関する計画を立てることなく実施してしまうと、効果的な育成はできません。
たとえば、新人研修の計画を立てることなく突発的または不定期に、研修用のマニュアルや素材も準備せずに実施してしまうと、育成を受ける側としてもどのようにスキルアップできるのかの見通しが立たず、意欲が低下してしまう可能性があります。
また、事前に計画を立てていないと適切なタイミングで育成が行えず、本当にそのときに必要な知識やスキルが得られない可能性もあるでしょう。
その場しのぎの単発実施ではなく、体系的な育成計画が求められます。
課題⑥目に見える効果を感じにくい
人材育成は行っているものの、目に見えるような効果が出ておらず、成功しているのか失敗しているのか判断できないことがあります。
そもそも、成功したからといってすぐに数字につながるわけではないので、目に見える効果を感じにくいのは不可避な側面があるとも考えられます。
効果のない育成を継続しても時間とコストばかりがかかってしまうことになるので、注意が必要です。
研修や育成を行う場合は、研修後アンケートのほか、理解度テストなども組み合わせて効果測定を行っていきましょう。
人材育成の課題を解決するために押さえるべきポイント
紹介した課題を解決するためには、どのように取り組んでいけばよいのでしょうか。
効果的な方法を8つ解説します。
ポイント①人材育成に充てる時間を確保する
当たり前のことではありますが、そもそも人材育成に充てる時間を確保できなければ始められません。
「誰か手が空いたときに」と考えてしまうと計画的な育成を実施するのは難しくなり、場合によってはまったく育成ができていないといった事態も考えられます。
そこで重要なのが、あらかじめ育成計画を立て、その内容に応じて社内の業務や人員配置を調整し、育成の時間を組み込むことです。
研修やOJTの内容・実施時期・所要時間などを明確にした上で、日々の業務と両立できる体制を整えていくことが求められます。
人手不足であるために時間を確保できない場合は、外部セミナーの活用も有効な手段のひとつです。
ポイント②育成担当者のスキル向上を図る
育成担当者のスキルが不足していると感じる場合は、先にその問題からクリアしていかなければなりません。
育成担当者には、目標管理能力のほか、コミュニケーションスキル、論理的な思考のためのロジカルシンキングなどのスキルが必要です。
また、指導者として必要な「教えるためのスキル」を身につけていきましょう。
社内だけではリソースが不足している場合は、指導者向けのセミナーも活用してみてはいかがでしょうか。
ポイント③人材育成に関する制度を整備する
人材育成の方法を検討し、それに応じた制度を整備することが求められます。
たとえば、活用できる制度やシステムとして、以下が代表的です。
【役立つ制度・システム】
- 社内・外部研修:社員のスキルアップ・能力開発のために行う研修
- OJT:実際の業務を行う中で職務に必要な能力を習得させる手法
- OFF-JT:実際の職場以外で行う集合研修などの手法
- メンター制度:立場の近い先輩の従業員が精神的な部分をサポートする制度
- ジョブローテーション制度:定期的に職種・部署を移動させる制度
- 目標管理制度:社員本人に目標を設定させ、達成度合いを評価する制度
- e-ラーニング:オンラインシステムを活用した学び
自社に適したものを検討していきましょう。
ポイント④人材育成の目的と目標を明確化する
何のために人材育成を行うのか目的や目標を明確化しておかないと、実践すべき育成が見えてきません。
詳細に決める前に育成を始めてしまうと、内容がぶれてしまうこともあるため、注意が必要です。
人材育成を行うこと自体が目標ではありません。
どのようなスキルを身につけてほしいのか、どういった人材になってほしいのか具体的な数字を盛り込みながら目標設定することが大切です。
ポイント⑤自主性や自発性を養う
自主性や自発性を養うことも大切です。
自主性とは、自身の判断のもとで決められたことを実践していくことを指します。
一方で、自発性とは誰かに指示されることがなくても率先して取り組んでいくことです。
どちらも重要と言えます。
たとえば、会社が用意した研修をただ受け身で受講しているだけでは、自主性や自発性はなかなか養われません。
社員自身が「なぜ学ぶのか」「どう活かすのか」を考える機会を与えることが重要です。
そのためには、日々の業務の中で改善提案を求めたり、自ら課題を見つけて行動に移せる環境を整備したりといった工夫が求められます。
また、スキルアップのために社員が自ら資格試験や講座を探して受講するなど、主体的な学びを後押しする制度や支援体制を整えることも有効です。
こうした取り組みにより、単なる知識の習得にとどまらず、組織全体としての自走力・実行力を高めることができます。
ポイント⑥期日を設定する
あらかじめ目標を明確にしておき、それをいつまでに達成するのか期日を設定しておきましょう。
期日を設定することで、育成の進捗を確認しやすくなります。
進捗状況に応じて、育成計画の修正が必要となる場合もあります。
期日を設定する際は、達成可能なものにすることが重要です。
定めておいた目標を達成するのにかかる期間から逆算する形で目標を決めておくと、適切でない期日設定を避けることができます。
ポイント⑦スキルを可視化する
どのような育成が必要なのか判断するために、スキルを可視化しておきましょう。
一般的な方法といえば、スキルマップの作成です。
また、評価シートなどを活用することにより、本人はもちろん、上司、組織で成長を実感できるようになります。
スキルの可視化は、モチベーションの維持に寄与する重要な要素です。
ポイント⑧最適な育成スキームを取り入れる
各従業員の立場や役職に応じた育成スキーム(研修内容やスケジュールの枠組み)を取り入れましょう。以下のようなものがあります。
新入社員の育成
新入社員には、業務遂行に必要な基礎的なスキルと知識の習得が求められます。
また、学生気分が抜けない新入社員もいるため、社会人としての意識を醸成する育成スキームの導入が必要です。
業務に関する不安を解消するため、OJTやOFF-JTに加え、相談しやすいメンター制度の整備も検討しましょう。
中堅社員の育成
中堅社員は、日々の業務に慣れてくる段階にあります。
この段階ではモチベーションの低下やスキルアップの停滞が懸念されるため、モチベーションを維持できる育成スキームの導入が必要です。
ジョブローテーションで気持ちを新たにしてもらうのもよいでしょう。
また、管理職へのキャリアアップを考えると新入社員だけではなく、中堅社員に対しても外部セミナーやスキルアップ研修が必要です。
リーダーの育成
リーダー層はチームを率いる立場であるため、業務の遂行に加え、メンバー育成に関する知識や経験が必要です。
また、従業員をまとめるためには、自身の業務遂行とは異なる知識の習得も求められます。
上司と部下を橋渡しする役割を担うことも多いため、コミュニケーション能力の向上が重要です。
人事評価研修や、外部研修などを活用してみてはいかがでしょうか。
管理職の育成
管理職の中でも昇進したばかりの人へは、自身がもっている役割を認識するための育成が必要です。
一方で、ある程度経験を積んで中級管理職となった人や、上級管理職となった人とでは、行うべき育成が変わってきます。
リーダー以上に責任の重い立場になるため、自身に求められる責任を果たしつつ、部下をマネジメントする能力が求められます。
そのためには、外部研修の活用も効果的です。
また、自発的にスキルアップへ取り組めるよう、資格取得支援や学習費用補助など、自己研鑽を後押しする制度の整備が望まれます。
関連記事
「社内教育とは?代表的な方法と効率的に行うためのポイント」
フィンテックスでは、お客様のご予算に応じて「マニュアルのあるべき姿」を、さまざまな視点からご提案しています。
他社には無い、コンサルティングがフィンテックスの強みです。
お客様の現状をヒアリングし、ご希望・ご要望を伺ったうえで業務改善につなげるマニュアルを作成いたします。
詳しいマニュアル制作の実績については、以下をご覧ください。
業務マニュアル 超大型の業務マニュアル編纂プロジェクト。制作チームを編成した初動準備、さまざまなドキュメント制作の提案や柔軟な対応、20,000ページ以上のマニュアル作成、細やかなフォローなど。途中からチームを拡大し、柔軟な対応でご評価いただきました。 業務マニュアル データ形式も見た目もバラバラだったマニュアルを読みやすい構成に作り直し、写真画像の補正、印刷、製本までを一括で対応しました。現場で活用できる「使える」マニュアルになったとご評価いただきました。 いかがだったでしょうか。 企業の人材育成で抱えやすい主な課題と、解決策について解説しました。 課題を放置してしまうと、社員の成長が停滞し、生産性の低下や離職率の上昇など、企業全体への悪影響につながる恐れがあります。 まずは自社の現状を把握し、課題に応じた育成計画を策定した上で、実効性のある取り組みを段階的に進めていくことが重要です。 早期に対策を講じることで、持続的な組織の成長につなげていきましょう。 人材育成の場面で役立つマニュアルを作成するのもおすすめです。 内容をマニュアルでまとめておけば、育成担当によって育成の内容やレベルが違うといったことも起こりにくくなります。 フィンテックスでは各種業務マニュアルの作成を行っているので、ぜひご相談ください。 監修者 企画営業部 営業本部長 / 経営学修士(MBA) <略歴> フィンテックスにて、マニュアル作成に関する様々な顧客課題解決に従事。
金融系からエンターテインメント系まで様々な経験から幅広い業務知識を得て、「分かりやすいマニュアル」のあるべき姿を提示。500社以上のマニュアル作成に携わる。また、複数の大企業でマニュアル作成プロジェクトの外部マネージャーを兼務している。
趣味は茶道。
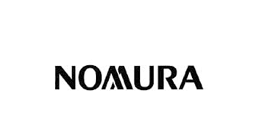

課題解決に向けた取り組みが求められる

月刊エコノミスト・ビジネスクロニクルで取材していただきました。ぜひご覧ください。
https://business-chronicle.com/person/fintecs.php
マニュアルアカデミー
最新コンテンツ

金融業務マニュアル作成のポイントと制作事例を紹介
2025.12.26
マニュアルのご相談・お問い合わせ
マニュアル作成に関するご相談やお悩みがございましたら、お気軽にお問い合わせください。
-
24時間受付中!
翌営業日にご連絡いたします。 -
資料を無料配布中!
マニュアル作成のコツを伝授します。








